本件では、イ号物件の構成についても当事者間で争いになりましたが、誌面の関係上、本稿では裁判所の認めた構成を前提にすることにします。
そのほか、無効論等も争点となりましたが、
I.イ号物件が本件特許発明の技術的範囲に含まれるか
II.含まれないとしても、均等と認めることはできるか
の2点について主に争われました。
Iの争点について、当事者で争いになったのは、本件特許発明の構成要件D「当該固定棚の先端の円形孔からなる支持部に対して上記外管をその伸縮に応じて摺動自在に挿通して該固定棚を水平に支持し、」(下線部は訂正部分)のうち「円形孔」の解釈及び構成要件充足性であります。
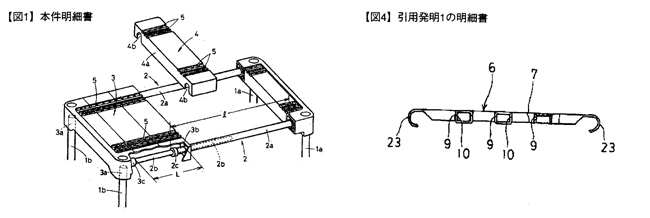
上記本件明細書の図1の「3b」が「円形孔からなる支持部」に該当する箇所になります。
一方、イ号物件の「円形孔からなる支持部」に該当する構成は、「下半分が円形で上半分が角丸略四角形であり中央部から下方に向かって突出片を有する孔からなる支持部」であります。
被控訴人は、「円形孔からなる」という限定は、引用発明1(特開平9−308532)の湾曲掛止部23の構成(円形の一部が開放された断面形状)を回避するため、かかる限定を付したものであって、一部が開放された形状のものを除外することに技術的意味があり、周囲が完全に取り囲まれた形状のものであれば真円形に限定されないと主張しました。
上記引用発明1の明細書の図4の「23」が「湾曲掛止部23」に該当する箇所になります。
それに対し、控訴人は、本件訂正の経緯からすれば、「円形孔」は「断面が真円状の孔」を指すのは自明であるなどとして争いました。
また、IIの争点について、被控訴人は、支持部の上半分の形状は円形でないとしても、その相違は本件発明の本質的部分ではなく、また、「円形孔からなる」という限定は、イ号物件の支持部の形状を意識的に除外したものではないなどと主張しました。
それに対し、控訴人は、本件訂正により「着脱自在でない」などの作用効果を有することになったのであり、「円形孔」であることは本質的部分であって、当該訂正の経過に鑑みると「円形孔」は「断面が真円状の孔」に限定されるなどと争いました。
そのほか、無効論等も争点となりましたが、
I.イ号物件が本件特許発明の技術的範囲に含まれるか
II.含まれないとしても、均等と認めることはできるか
の2点について主に争われました。
Iの争点について、当事者で争いになったのは、本件特許発明の構成要件D「当該固定棚の先端の円形孔からなる支持部に対して上記外管をその伸縮に応じて摺動自在に挿通して該固定棚を水平に支持し、」(下線部は訂正部分)のうち「円形孔」の解釈及び構成要件充足性であります。
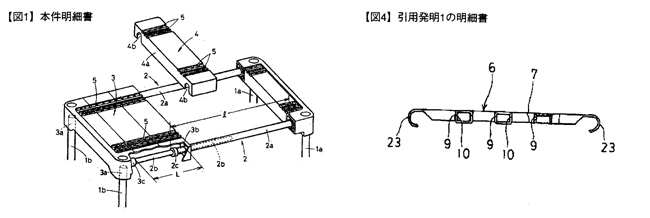
上記本件明細書の図1の「3b」が「円形孔からなる支持部」に該当する箇所になります。
一方、イ号物件の「円形孔からなる支持部」に該当する構成は、「下半分が円形で上半分が角丸略四角形であり中央部から下方に向かって突出片を有する孔からなる支持部」であります。
被控訴人は、「円形孔からなる」という限定は、引用発明1(特開平9−308532)の湾曲掛止部23の構成(円形の一部が開放された断面形状)を回避するため、かかる限定を付したものであって、一部が開放された形状のものを除外することに技術的意味があり、周囲が完全に取り囲まれた形状のものであれば真円形に限定されないと主張しました。
上記引用発明1の明細書の図4の「23」が「湾曲掛止部23」に該当する箇所になります。
それに対し、控訴人は、本件訂正の経緯からすれば、「円形孔」は「断面が真円状の孔」を指すのは自明であるなどとして争いました。
また、IIの争点について、被控訴人は、支持部の上半分の形状は円形でないとしても、その相違は本件発明の本質的部分ではなく、また、「円形孔からなる」という限定は、イ号物件の支持部の形状を意識的に除外したものではないなどと主張しました。
それに対し、控訴人は、本件訂正により「着脱自在でない」などの作用効果を有することになったのであり、「円形孔」であることは本質的部分であって、当該訂正の経過に鑑みると「円形孔」は「断面が真円状の孔」に限定されるなどと争いました。