原告(株)自然健康館は、指定商品を第29類「海藻エキスを主材料とする液状又は粉状の加工食品」、第32類「清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース」とする商標「『自然健康館』と『スーパーフコイダン』からなり、両者を2段併記したもの」を有しておりました。
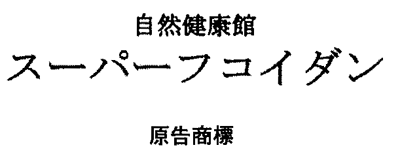
そこで、原告は被告に対し、被告標章は原告の商標権を侵害しているとして、被告標章を使用することの差し止め、損害賠償の支払い等を求めて、平成18年に東京地方裁判所に訴えを提起いたしました。
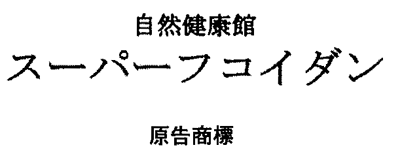
そこで、原告は被告に対し、被告標章は原告の商標権を侵害しているとして、被告標章を使用することの差し止め、損害賠償の支払い等を求めて、平成18年に東京地方裁判所に訴えを提起いたしました。