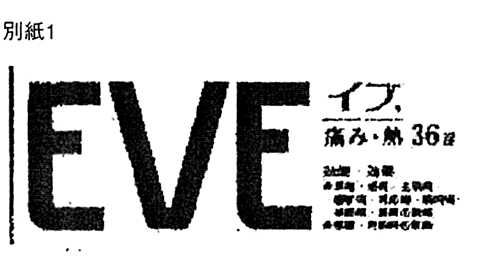
| 知的財産権判例ニュース |
| 商標法53条1項所定の商標の不正使用を認めた事例 |
|---|
|
(知的財産高等裁判所 平成19年2月28日判決 平成18年(行ケ)10375号) |
| 水谷直樹 |
| 1.事件の概要 |
原告エスエス製薬(株)は、指定商品を第1類「化学品、薬剤、医療補助品」とする商標「イブ」、同じく指定商品を第5類「薬剤、歯科用材料、医療用油紙」等とする商標「イブ」および「EVE」を、それぞれ登録商標として有しておりました(登録第1598640、3065022、3065023号)。原告は、これと共に、自社商品の鎮痛・解熱剤の製品パッケージ上に別紙1の表示もしくはこれに類似する標章を付して販売しておりました。
これに対して、被告東光薬品工業(株)は、指定商品を第5類「薬剤、医療用油紙」等とする商標「イブペイン」を登録商標として有しておりました(登録第3260011号)。 被告は、これと共に「イブペイン Evepain」との名称の鎮痛・解熱剤(被告商品)を製造販売し、平成14年以降は、被告商品は、被告商標の通常使用権者である三友薬品(製造元)、ラクール薬品販売(販売元)により、製造販売されておりました。 上記通常使用権者は、鎮痛・解熱剤である被告商品の製品パッケージ正面上に別紙2の表示を付しておりました。 そこで、原告が被告に対して、被告商品上の別紙2の表示は商標法53条1項所定の商標の不正使用に該当するとして、被告の登録商標の取消しを求めて、平成17年に取消審判を請求いたしました。 特許庁は、平成18年に被告商標の登録を取り消すことはできないと判断したために、原告は、当該審決の取消しを求めて知財高裁に審決取消訴訟を提起いたしました。 |
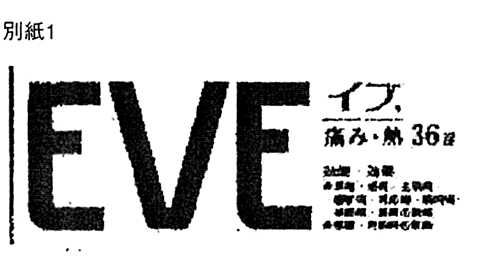

| 2.争点 |
|
本事件での争点は、被告商標の別紙2の態様での使用が商標法53条1項の規定要件に該当するのか否かでした。
|
| 3.裁判所の判断 |
|
知的財産高等裁判所は、平成19年2月28日に判決を言い渡しましたが、上記争点については、
「商標法53条1項は、商標権者からその商標権について通常使用権の許諾を受けた通常使用権者が、指定商品又はこれに類似する商品についての登録商標に類似する商標の使用であって他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判の請求をすることができるとして、使用権者の不正使用による商標登録取消審判の制度を定めている。」 「原告は、鎮痛・解熱剤である原告商品の製品パッケージ正面等に、別紙1のとおり、『EVE』の欧文字を大きく太字で横書し、その右横上段に『イブ』との小さな片仮名文字を配した引用商標(『イブ』の直下に『痛み・熱36錠』と付記されている。)及びそれに類似する標章を付して、昭和60年12月から販売を開始し、昭和61年1月、新聞、テレビ、業界紙において、原告商品の宣伝広告を行い、・・・・・・昭和61年度から平成15年度までの原告商品に係る原告の宣伝広告費は、対応する各年度において、6億7900万円、4億1400万円、2億9700万円、・・・・・・1億4900万円、1億3500万円、・・・・・・1億2500万円、1億0100万円、5500万円、5400万円であり、昭和61年度から平成15年度までの宣伝広告費は、合計35億6000万円である。 また、鎮痛・解熱剤の分野において、原告商品の市場シェアは、平成5年度、平成6年度、平成7年度において、それぞれ、7.1%、8.3%、9.0%で、いずれの年度も全国5位であり、平成13年度、平成14年度において、それぞれ12.1%、11.5%で、いずれの年度も全国4位であり、平成15年度、平成16年度、平成17年度において、それぞれ、12.7%、13.0%、13.4%で、いずれの年度も、『バファリン』、『ナロン』に次いで、全国3位である。平成17年度において、鎮痛・解熱剤全体の販売金額は、総額462億9670万円であり、そのうち、原告商品の販売金額は、62億1740万円である。 上記のような宣伝広告活動の規模やその態様、原告商品の市場シェアの比率や販売金額の大きさ、原告商品における引用商標の表示の態様等を総合すれば、引用商標は、原告の製造、販売に係る鎮痛・解熱剤である原告商品を表示するものとして、遅くとも、市場シェアについて証拠上全国5位であることが認められる平成5年ころまでに、すなわち、本件商標の商標登録出願前には、取引者、需要者に広く認識され、周知著名な商標になり、その後も、周知著名性を維持しているものと認められる。」 「本件使用商標と引用商標の類否、出所混同のおそれについて (1)本件使用商標は、 『EVEPAIN』の欧文字からなるものであるところ、被告商品における使用態様は、別紙2のとおり、『EVEPAIN』を製品パッケージ正面の上段に白抜きのややデザイン化した欧文字により大きく横書きしているものである。 『EVEPAIN』は、その下に付された片仮名文字からも、『イブペイン』との称呼を生ずるものであるが、それ自体、直ちに一体として特定の観念を生ずるものではない。 他方、『PAIN』ないし『pain』は、『痛み』等を意味する比較的平易な英単語であり、『ペイン』についても、『痛み。苦しみ。』(大辞林第三版)と説明され、・・・・・・そうすると、『EVEPAIN』のうち、『ペイン』の称呼を生じる『PAIN』の部分は、これに接した取引者、需要者に、『痛み』の観念を生じさせるものと認められ、特に、原告商品の製品パッケージ正面には、前記3(2)のとおり、『痛み・熱36錠』と付記されているところ、別紙2のとおり、被告商品の製品パッケージ正面にも『痛み・熱に』と記載されているように、被告商品は、鎮痛・解熱剤であって、『痛み』に関連する商品であり、被告商品においては、『痛み』は、商標が付された商品自体の特性に係るものであるから、このことからも、より一層、『EVEPAIN』のうち、『PAIN』の部分は、『痛み』との観念が生じ得るものということができる。 このことに、『EVE』の欧文字と『イブ』の片仮名文字からなる引用商標が、前記3(2)のとおり、鎮痛・解熱剤である原告商品を表示するものとして、周知著名な商標になっていたこと、被告商品も鎮痛・解熱剤であること、被告商品は、別紙2のとおり、製品パッケージにおいて、引用商標と同様、欧文字を大きく表示するという使用態様であること、『EVEPAIN』は欧文字の7文字で構成され、それを『EVE』と『PAIN』とに分離することが取引上不自然なほど、不可分に結合しているとまで断定することはできず、審決の『不可分一体に構成され・・・・・・『EVE』と『PAIN』とが軽重の差がなく結合し、分離不能なほどに、一体的な強い結合状態をなしている』(審決謄本15頁下から第2段落)との判断はにわかに首肯し難いことを併せ考慮すると、被告商品に付せられた本件使用商標である『EVEPAIN』に接した取引者、需要者は、それらを『EVE』と『PAIN』とからなるものと理解し、『EVE』の部分においては、周知著名な引用商標を想起するとともに、『PAIN』の部分は、『痛み』との観念を生じ、その商品の特性に係る部分であり、周知著名な引用商標に係る原告商品の関連商品の特性を示す部分として認識され、それ自体としては自他識別力を欠くものと認めるのが相当である。 そうすると、本件使用商標は、原告の製造、販売する鎮痛・解熱剤を表示するものとして周知著名である引用商標をその主要な構成部分に含む商標として、当該構成部分が他の部分から分離して認識され得るものであり、引用商標と観念において類似し、外観、称呼の一応の相違をしのぐものと認められる。 そして、本件使用商標を鎮痛・解熱剤である被告商品に使用したときは、本件使用商標と原告の引用商標とが類似することから、これに接した取引者、需要者に対し、その商品が原告又は原告と何らかの緊密な営業上の関係にある者の業務に係る商品であるかのように、その出所につき混同を生ずるおそれがあるというべきである。」 「以上によれば、本件通常使用権者による、本件商標に類似する本件使用商標の使用は、原告又は原告と何らかの緊密な営業上の関係にある者の業務に係る商品であるかのように、その出所につき混同を生ずるおそれがあるというべきであるから、これと異なる審決の判断は誤りというべきである。そして、本件商標の商標権者である被告は、商標法53条1項ただし書所定の事由、すなわち、本件通常使用権者の上記不正使用の事実を知らず、かつ、相当の注意をしていたことについては、何ら主張・立証しないのであるから、上記判断の誤りが審決の結論に影響することは明らかである。原告の取消事由1ないし3の主張は、以上の趣旨をいうものとして理由があり、審決は取消しを免れない。」 と判示して、原審決を取り消しました。 |
| 4.検討 |
|
本件は、商標法53条1項の適用が問題になった事例です。 同条は、商標権の通常使用権者が、当該商標を使用するにあたり、他人の業務に係る商品と混同を生ずる態様で使用した場合には、第三者からの請求により当該商標登録の取消しを認める制度であります。 本件においては、別紙2の表示が、商標法53条1項に該当する使用態様であるのか否かが問題になり、原審決はこれを否定いたしましたが、本判決はこれを肯定いたしました。 被告商標はカタカナ書きの「イブペイン」でありましたが、実際の使用態様は別紙2のとおり、「EVEPAIN」と「イブペイン」を上下2段に表示しておりました。 本判決は、原告の別紙1の引用商標が周知著名であることを認定したうえで、一方が「EVE」であり、他方が「EVEPAIN」であるとしても、引用商標の「EVE」が周知著名である以上、別紙2の「EVEPAIN」の表示態様は引用商標と類似しており、原告商品との間で出所の混同を来すおそれがあると認定しております。 本判決は、別紙1の引用商標と別紙2の本件使用商標とが類似する理由として、引用商標が、原告の製造・販売する鎮痛・解熱剤を表示するものとして周知著名な商標であることを前提としたうえで、本件使用商標は引用商標「EVE」を主要な構成部分として含み、かつ「PAIN」からは「痛み」との観念が生じるから、両者は相互に観念において類似すると判示しており、上記は、引用商標が周知著名であることを前提にしたうえでの類否判断であると考えられます。 本件は、商標の不正使用を認めた事例の1つとして、今後の実務において参考になるものと考えられます。 みずたに なおき 1973年東京工業大学工学部卒、1975年早稲田大学法学部卒業後、1976年 司法試験合格。1979年 弁護士登録、現在に至る(弁護士・弁理士、東京工業大学大学院特任教授、専修大学法科大学院客員教授)。 知的財産権法分野の訴訟、交渉、契約等を多数手掛けている。 |