
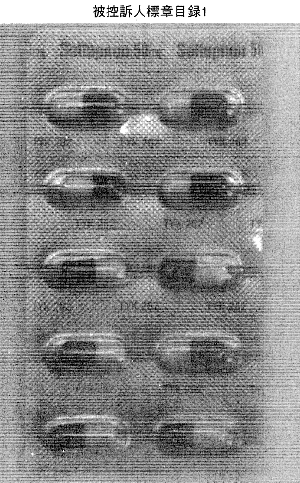
| 知的財産権判例ニュース |
|
医療用医薬品のカプセル、PTPシートの配色や表示に対する 不正競争防止法による保護が否定された事例 |
|---|
|
「知的財産高等裁判所 平成18年11月8日判決」 |
| 水谷直樹 |
|
1.事件の概要 |
控訴人エーザイ(株)は、医療用医薬品の胃潰瘍治療剤である「セルベックスカプセル50mg」を、昭和59年12月にPTPシートに装填された状態で、販売を開始いたしました。
同医療薬品のカプセルは、上半分が「灰青緑色不透明」、下半分が「淡橙色不透明」という配色からなり、カプセルを収納しているPTPシートは銀色地に青色の文字等を表示しておりました。 これに対して、被控訴人共和薬品工業(株)は、平成10年10月に販売名を「テルペノンカプセル50mg」とする医療用医薬品である胃潰瘍治療剤(ジェネリック医薬品)を販売開始いたしました。 同医薬品も、頭部が「灰青緑色」、胴部が「淡橙色不透明」の配色であり、これを収納するPTPシートは銀色地に青色の文字等を表示しておりました。 そこで、控訴人は被控訴人に対して、被控訴人による同医薬品の製造、販売行為が不正競争防止法2条1項1号に該当すると主張して、同医薬品の製造、販売の差止め等を求め、平成17年に東京地方裁判所に訴訟を提起いたしました。 東京地方裁判所は平成18年2月24日に判決を言い渡し、控訴人の請求を棄却したため、控訴人が知財高裁に控訴したのが本事件です。 なお、付言いたしますと、控訴人は、本事件以外にも、筆者が確認しただけでも合計7件の同種訴訟を東京地裁に提起しており、いずれにおいても胃潰瘍治療剤のカプセルおよびPTPシートにつき同様の差止請求等を行いましたが、結果としてすべて請求棄却の判決を受けております。 そこで、控訴人は、これらの判決に対して知財高裁に控訴を行ったところ、平成18年9月27日に2件、翌9月28日に3件、同11月8日に3件の判決が、それぞれ言い渡されました。 本稿で紹介いたしますのは、これらのうちで平成18年11月8日に言い渡された判決のうちの1件についてであります。 |

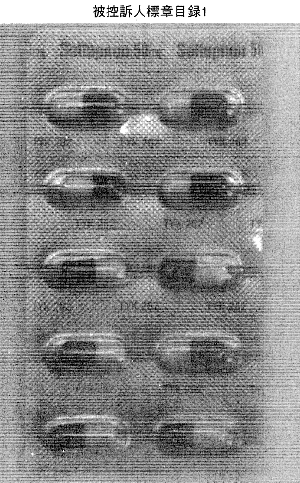
|
2.争点 |
|
本事件での争点は、控訴人の医薬品のカプセルおよびPTPシートの配色、表示等が、不正競争防止法2条1項1号所定の商品等表示に該当するか否かでありました。
|
|
3.裁判所の判断 |
|
知財高裁は、平成18年11月8日に判決を言い渡しましたが、
「商品としての医療用医薬品のカプセル及びPTPシートの配色が不正競争防止法2条1項1号の『商品等表示』に当たり得るかどうかにつき検討する。 控訴人商品のようなカプセル剤においては、カプセルは商品そのものに当たるところ、商品の配色は、通常、商品の出所表示機能を持たせることを目的とするものではないが、それが、それ自体として極めて特異なものであったり、あるいはそうでなかったとしても、特定の者による長期間の独占的な使用、極めて強力な宣伝広告活動、圧倒的な販売実績等があって、需要者において、当該配色のカプセルが、特定の事業者の出所を表示するものとして周知となっている場合には、その商品等表示性を否定する理由はない。また、PTPシートは、不正競争防止法2条1項1号の『商品の・・・・・・包装』に当たるものの、その配色自体は、通常、商品の出所表示機能を持たせることを目的とするものではない点で、カプセルと同様であり、したがって、これに商品等表示性を認めるためには、前同様、それ自体として極めて特異なものであったり、あるいはそうでなかったとしても、特定の者による長期間の独占的な使用、極めて強力な宣伝広告活動、圧倒的な販売実績等があって、需要者において、当該配色のPTPシートが、特定の事業者の出所を表示するものとして周知となっていることを要するものと解するのが相当である。」 「(1)需要者について 医師及び薬剤師等の医療関係者が、医療用医薬品の需要者であることは、当事者間に争いがない。 患者が医療用医薬品の需要者であるか否かの点につき、控訴人は、患者は、・・・・・・商品選択の主体であって、需要者であると主張する。 しかしながら、患者が購入する具体的な医療用医薬品は、医師の処方によって(医師が、医薬品の一般名をもって処方した場合には、薬剤師の調剤によって)決定されるものであり、これらの処方や調剤は、ともに極めて専門的な知識、経験に基づき、かつ、業務上の責任を伴って行われる選択行為である。 ・・・・・・患者の要望に従ったからといって、処方、調剤をした医師や薬剤師の業務上の責任が解除されるわけではないから、たとえ、結果的に患者の要望のとおりとなったとしても、医療用医薬品の選択の主体が医師や薬剤師であることにいささかの変わりもない。 ・・・・・・そうすると、患者の要望は医師や薬剤師の選択の参考と位置付けられるにすぎず、患者について、医療用医薬品の需要者という程度にまで、その選択に係る主体性を認めることはできない。」 「(2)判断の対象となる市場について 控訴人は、医師や薬剤師が、自己の専門に係る限られた領域の医療用医薬品と日常的に接し、当該領域に係る医療用医薬品の需要者でしかないとして、控訴人商品の配色が商品等表示性を有するかどうかは、胃潰瘍治療剤の市場を対象として判断すべきであると主張する。 しかしながら、医師や薬剤師が、それぞれの専門領域を有していることはそのとおりであるとしても、医師等が現実にその領域の疾患に対処するという意味での専門領域は、大都市の基幹病院の勤務医等を想定した場合であっても、例えば、胃潰瘍治療のみというまでに細分化されているのが一般的であるとは到底考えられず、内科あるいは消化器内科という程度の広さを有するのが通常であり、さらに、いわゆる医療過疎地帯などにおいて医療に従事する医師等であれば、専門領域などないに等しいほど、幅広い領域の疾患に対処せざるを得ないことは、公知の事実である。 そうであれば、医師や薬剤師は、日常、胃潰瘍治療剤だけでなく、広範囲の医療用医薬品を取り扱っていることが通常であるというべきであるから、控訴人商品の配色が商品等表示性を有するかどうかは、カプセル剤である医療用医薬品全体の市場を対象として判断すべきものであり、控訴人の上記主張を採用することはできない。」 と判示したうえで、 「(3)控訴人商品のカプセル及びPTPシートの配色の商品等表示性の有無について ア 控訴人商品の・・・・・・カプセル及びPTPシートの配色は、それ自体として極めて特異ということはできないから、以下、控訴人によるこれらの配色の長期間にわたる独占的な使用、極めて強力な宣伝広告活動、圧倒的な販売実績等があったことにより、需要者において、カプセル及びPTPシートの上記配色が、これに係る商品の出所が控訴人を表示するものとして周知となっている場合に当たるかどうかを検討する。 イ 控訴人商品は昭和59年12月6日に販売が開始されたところ、控訴人は、遅くとも平成4年ころから現在まで、1000人前後のMRを通じ、全国の医師及び薬剤師に対し、製品便覧やチラシ等を配布して、控訴人の販売に係る他の医薬品とともに、控訴人商品に関する情報提供及び宣伝活動を行ってきたこと、・・・・・・販売名を『セルベックス』とする医療用医薬品の年間売上高は、発売開始の翌年である昭和60年には30億円であったものの、その後増え続けて平成7年にはピークとなる482億円に達したが、その後は概ね下降傾向をたどり、平成8年は456億円、平成9年は437億円、平成15年は244億円であったこと、・・・・・・『セルベックス』は、医師によって処方された数量のランキングにおいて、全医薬品を対象とした場合、病院での処方については、平成12、13年が2位、平成15、16年は4位であり、開業医による処方については、平成12年が3位、平成16年が7位であり、A2B抗潰瘍剤を対象とした場合には、病院での処方及び開業医による処方とも、平成12年から平成16年まで1位であったことが認められる。 ウ 控訴人商品の販売開始時である昭和59年12月当時、既に販売が開始されていた医療用医薬品のうち、別表1(編集部注・省略)記載のものに係るカプセルが、控訴人商品と同様、緑色と白色ないし淡橙色の配色であったこと、及び判明する限りのPTPシートの配色は同表のとおりであることが認められる。 ・・・・・・また、別表2(同省略)に掲記の各証拠によれば、昭和59年12月以降に販売が開始され、現在に至っている医療用医薬品(控訴人商品に係るジェネリック医薬品を除く。)のうち、別表2記載のものに係るカプセルが、控訴人商品と同様、緑色と白色ないし淡橙色の配色であったこと、及び判明する限りのPTPシートの配色は同表のとおりであることが認められる。 さらに、・・・・・・平成9年から平成11年にかけて被控訴人商品以外に9種類の控訴人商品に係るジェネリック医薬品の販売が開始され、現在に至っているが、これらの医薬品のカプセルも、控訴人商品と同様、緑色及び淡橙色の配色であったことが認められる。 また、上記各医薬品について、その販売量や売上高を明らかにする証拠はないが、・・・・・・医療用医薬品は、需要者が店舗の販売棚で手に取って初めてその存在を知るような性質の商品ではなく、・・・・・・販売量等が重要な要素となるものとはいえない。 エ 次に、実際の医療用医薬品の選択が行われる状況を考えると、医師は、通常は、処方せんに医薬品の販売名を記入することにより、その選択を行うものであって(例外的に、一般名が処方せんに記載された場合には、医師は、具体的な商品の選択を行わなかったことになる)、医薬品の現物を患者に交付することが通例であるとは考えることはできないから、カプセルやPTPシートの配色が類似する別の医薬品が存在したからといって、それがために識別を(すなわち、処方せんに記入すべき医薬品の販売名を)誤るという事態は容易に想定することができない。 薬剤師については、処方せんに医薬品の販売名が記載されていたときはそれに従って、一般名が記載されていたときは、自らの選択により、特定の医薬品を調剤して、患者に交付するものであるから、カプセルやPTPシートの配色が類似した別の医薬品があった場合に、その配色に頼って、識別を(すなわち、患者に交付する医薬品を)誤るという事態が想定できないわけではない。しかしながら、・・・・・・現在は、処方せんに販売名が記載される場合が圧倒的に多いところ、そのような場合に、上記のような識別の誤りをすれば、たとえ、故意によるものではないにせよ、薬剤師法23条2項に違反することとなるのであるから、そう度々起こる事態とは考え難い。 そうとすれば、医師及び薬剤師の処方、調剤に係る医療用医薬品の選択、識別に当たって、カプセルやPTPシートの配色が果たす役割はかなり小さいものと認められる。 オ 以上によれば、控訴人は、控訴人商品の販売を開始した昭和59年12月以降、現在に至るまで、控訴人商品につき、需要者である医師等に対し、大規模な宣伝活動をしてきたことが認められるが、その販売実績では、胃潰瘍治療剤のうちではトップクラスのシェアを確保してきたとはいえ、他を圧倒するといえる程度であったことを認めるに足りる証拠はない。また、カプセルやPTPシートの配色については、最初に控訴人商品についてのジェネリック医薬品の販売が開始された平成9年当時においても、その後現在に至るまでの間においても、控訴人が独占的な使用をしてきたことを認めるに足りる証拠はなく、かえって、控訴人商品の販売が開始される前を含めたいずれの時期においても、カプセル剤である医療用医薬品であって、控訴人商品と類似したカプセルの配色や、PTPシートの配色を使用しているものが存在していたことが認められる。 そうすると、本件口頭弁論終結の日(平成18年9月13日)においても、損害賠償請求に係る期間の初日(平成14年3月24日)においても、控訴人商品のカプセルの配色及びPTPシートの配色が、これに係る商品の出所が控訴人を表示するものとして、需要者の間で周知となっているものと認めることはできない。 したがって、控訴人商品のカプセルの配色及びPTPシートの配色に、不正競争防止法2条1項1号の商品等表示性を認めることはできない。」 と判示して、控訴人の控訴を棄却いたしました。 |
|
4.検討 |
|
本事件では、医療用医薬品であるカプセル製剤のカプセルの配色およびこれを収納するPTPシートの地色および文字の配色が、不正競争防止法2条1項1号所定の商品等表示に該当するのか否かが争われました。
本判決は、引用のとおりの理由でこれを否定いたしましたが、知財高裁のこれ以外の7件の判決においても、同様の結論が出されております。 本事件の背景としては、医療用医薬品市場において、同種同効の医薬品が、いわゆる先発品と後発品(ジェネリック)として併存して販売されているとの事情があります。 このため、本事件と同種の係争は10年以上前から存在しておりましたが、不正競争防止法によりカプセルやPTPシートの配色、文字表示等の保護を認めることについては、個別の事実関係に依存するとはいえ、それほど容易ではないというのが一般の見方ではなかったかと考えられます。 本判決は、知財高裁において、この点に関する裁判所の見解が明確にされた点に意義があると考えられ、今後の同種事案の参考になるものと考えられます。 |