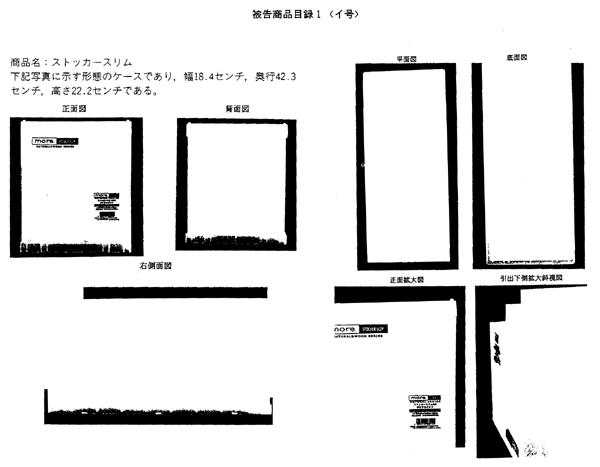原告リス(株)は,ポリプロピレン製の収納ケースを製造し,原告(株)良品計画は,これを販売してきました(原告商品目録1を参照)。
これに対して,被告(株)伸和が類似品の販売を開始したため(被告商品目録1<イ号>を参照),原告らは被告に対して,被告の行為は不正競争防止法2条1項1号または3号に該当する不正競争行為であるとして,被告製品の製造,販売等の差止めを求めて,平成15年に東京地方裁判所に訴えを提起しました。
東京地方裁判所は,平成16年7月14日に判決を言い渡し,原告らの請求を棄却いたしました。
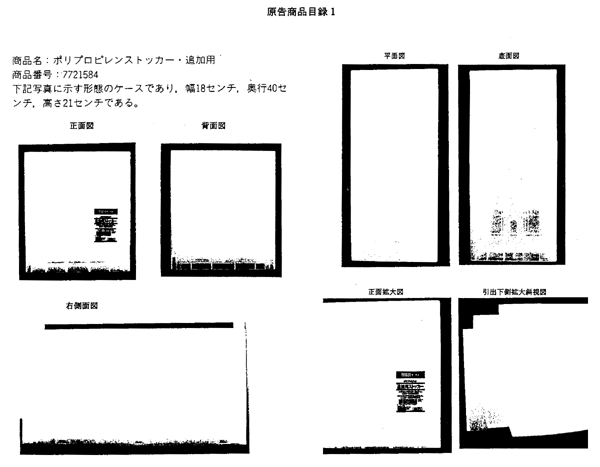
なお,東京地方裁判所は,同判決中で,原告商品の形態については,
「原告商品の共通の形態
原告商品は,以下の共通の形態を有している(以下これらを順に『共通形態(ア)』,『共通形態(イ)』などといい,併せて『共通形態』という。)。
(ア)左右の2枚の側板,底板及び後板からなり,前部及び上部が開口した四角枠状の本体の上部の開口部に四角板状の蓋がはめ込まれている。
(イ)前板,左右2枚の側板,底板及び後板からなり,上部が開口した四角容器状の引き出しが,ケース本体に引き出し自在に収納されている。
(ウ)引き出しの前面下部に幅方向に延びて引手部が形成されている。
(エ)ケース本体,引き出しは,共に乳白色半透明である。
(オ)本体は,隅部がすべて直角に処理されて丸みがなく,側面も上下にわたり面一に処理されている。
(カ)引き出しの前面の板は,よく注意して観察して初めて気がつく程度のごく小さな角度で傾斜している。
(キ)引手部は,引き出しの前面下部を全幅にわたり凹入させるとともに,引き出しの前面の板の下部裏側に指掛け用の溝が全幅にわたり形成されている。」
であるが,これらのうちで(ア)ないし(ウ)の特徴を備えている収納ケースが,原告商品発売以前から販売されており,また,(エ)ないし(キ)のうちのいくつかの点を備えた収納ケースも販売されていたことを認定して,原告商品の上記共通形態は,原告商品に独特な特徴的形態であるとはいえないと判示しております。
これに対して原告らが東京高等裁判所に控訴したのが,本事件です。
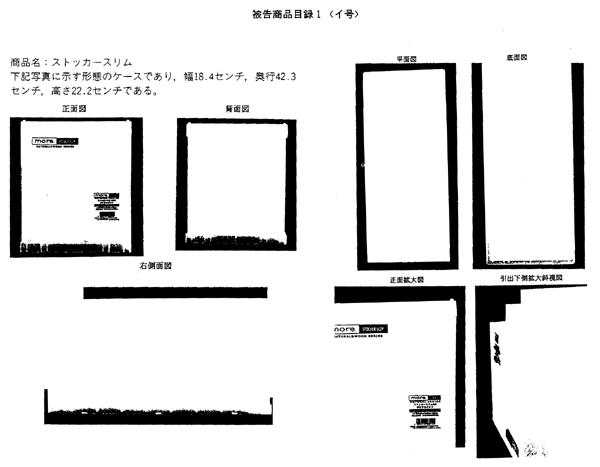
これに対して,被告(株)伸和が類似品の販売を開始したため(被告商品目録1<イ号>を参照),原告らは被告に対して,被告の行為は不正競争防止法2条1項1号または3号に該当する不正競争行為であるとして,被告製品の製造,販売等の差止めを求めて,平成15年に東京地方裁判所に訴えを提起しました。
東京地方裁判所は,平成16年7月14日に判決を言い渡し,原告らの請求を棄却いたしました。
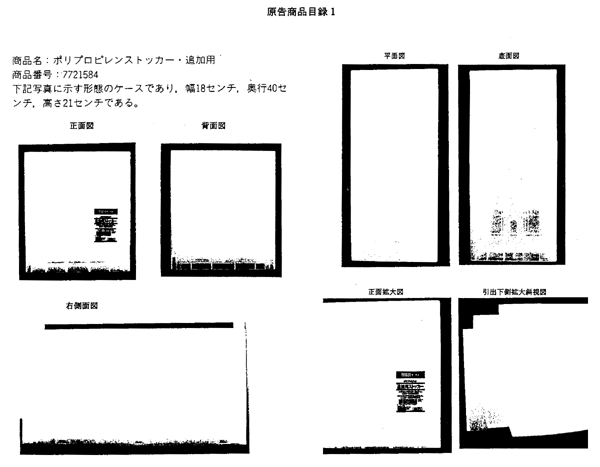
なお,東京地方裁判所は,同判決中で,原告商品の形態については,
「原告商品の共通の形態
原告商品は,以下の共通の形態を有している(以下これらを順に『共通形態(ア)』,『共通形態(イ)』などといい,併せて『共通形態』という。)。
(ア)左右の2枚の側板,底板及び後板からなり,前部及び上部が開口した四角枠状の本体の上部の開口部に四角板状の蓋がはめ込まれている。
(イ)前板,左右2枚の側板,底板及び後板からなり,上部が開口した四角容器状の引き出しが,ケース本体に引き出し自在に収納されている。
(ウ)引き出しの前面下部に幅方向に延びて引手部が形成されている。
(エ)ケース本体,引き出しは,共に乳白色半透明である。
(オ)本体は,隅部がすべて直角に処理されて丸みがなく,側面も上下にわたり面一に処理されている。
(カ)引き出しの前面の板は,よく注意して観察して初めて気がつく程度のごく小さな角度で傾斜している。
(キ)引手部は,引き出しの前面下部を全幅にわたり凹入させるとともに,引き出しの前面の板の下部裏側に指掛け用の溝が全幅にわたり形成されている。」
であるが,これらのうちで(ア)ないし(ウ)の特徴を備えている収納ケースが,原告商品発売以前から販売されており,また,(エ)ないし(キ)のうちのいくつかの点を備えた収納ケースも販売されていたことを認定して,原告商品の上記共通形態は,原告商品に独特な特徴的形態であるとはいえないと判示しております。
これに対して原告らが東京高等裁判所に控訴したのが,本事件です。