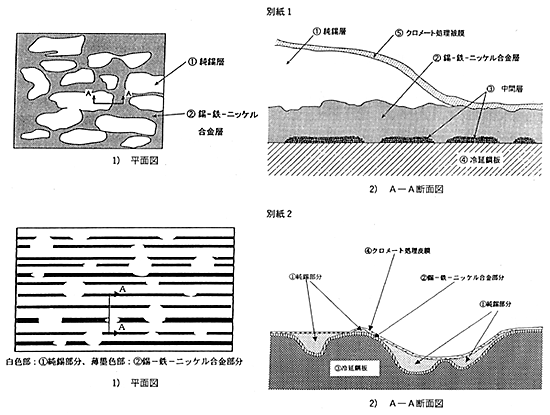
| 知的所有権判例ニュース |
| 本件鋼板の構成が特許発明の構成要件を 充足するか否かの証明が不可能であるとされた事件 |
|---|
|
「平成15年9月16日 東京高裁判決 平成15年(ネ)282号事件」 |
| 生田哲郎 高橋 淳 |
| 1.事件の概要 |
(1) 本件は,特許権者である控訴人(以下「原告」といいます)が,被控訴人(以下「被告」といいます)の行う,表面処理鋼板(以下「本件鋼板」といいます)が,原告の特許発明の技術的範囲に属するとして,損害賠償を求めた事案であり,大手の製鉄会社間の争いであること,50億円もの損害賠償を求めたことなどから注目を集めました。本件判決は,原審(東京地方裁判所:平成14(ワ)8729号)を維持し,控訴を棄却しておりますが,非侵害の結論の理由として,本件鋼板の構成が特許発明の構成要件を充足するか否かの証明が不可能であることが付加された点で,興味深いケースです。
(2) 本件特許発明は,表面に特殊な処理が施された鋼板に関するものであり,構成要件に分説すると,以下のとおりです。 鋼板面に下層側から, (i) 鉄メッキ,ニッケルメッキおよびクロムメッキの1種または2種以上,または鉄メッキ,ニッケルメッキおよびクロムメッキの1種または2種以上と錫メッキとの複層メッキ,若しくは鉄―錫合金メッキ,ニッケル―錫合金メッキおよびニッケル―鉄合金メッキの1種からなるメッキ付着量10〜500mg/m2の下地メッキ層, (ii) 錫合金層, (iii) 錫合金層上に不連続状に形成される純錫層, (iv) 付着量2〜30mg/m2の金属クロムとクロム換算で付着量3〜23mg/m2の水和酸化クロムとからなるクロメート処理被膜を有し,前記錫合金層および純錫層を合わせたトータル錫メッキ付着量が500〜2000mg/m2であることを特徴とする表面処理鋼板。 本件特許発明は,表面処理鋼板,特に溶接缶用素材として好適な表面処理鋼板に関し,低錫メッキ付着量でありながら優れた溶接性,耐食性を有する表面処理鋼板を提供するものです(本件明細書:1欄21行目から24行目)。その課題の解決手段は,表面処理鋼板の被膜構造を,錫メッキと特定成分及び付着量の下地メッキ及び後処理被膜との組み合わせによる複合被膜構造とし,しかも錫メッキのメッキ付着量とともにその付着構造そのものを特定することにあります(本件明細書:3欄3行目から11行目)。 (3) 他方,本件鋼板の構成に関しては,構成要件(i)の「下地メッキ層」に関する部分の構成について争いがありました。すなわち,原告は,「本件鋼板の構成は別紙1のとおりであり,本件鋼板には,錫合金層と冷延鋼板との間に,電気メッキに由来するニッケル―鉄の合金層からなる中間層が存在する」と主張しました。これに対し,被告は,「本件鋼板の構成は別紙2のとおりであり,本件鋼板には,錫合金層と区別される中間層は存在しない」と主張しました。但し,原告が中間層と指摘する部分には,そのすべての階層部分において,鉄,ニッケル及び錫が存在することについては争いがありませんでした。結局,本件鋼板の構成についての争点は,原告が中間層と指摘する部分に存在する錫が単なる不純物であり,当該部分はニッケル―鉄の合金層からなるといえるか否かという点に尽きます。 (4) 本件では,構成要件の意義・解釈も争われておりますが,目新しい判断はないため,本稿では,上記の本件鋼板の構成に関する争点を検討することとします。 |
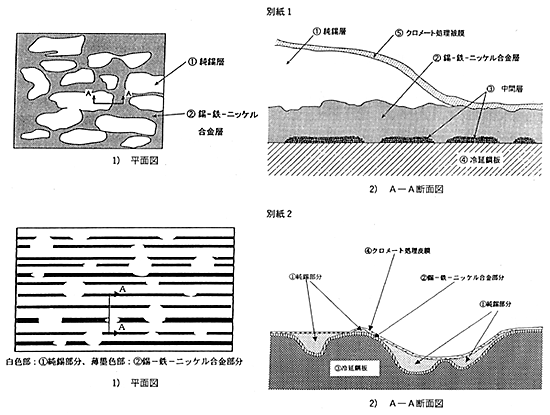
| 2.東京地方裁判所(平成14(ワ)8729号)の判断 |
|
被告製品の構成については,原告に立証責任がありますから,本件において原告が勝訴するためには,原告は,本件鋼板において,原告が中間層と指摘する部分に存在する錫が単なる不純物であり,当該部分は,構成要件(i)のニッケル―鉄の合金層からなるといえることを立証する必要があります。ここに「立証する」ということの意味は,裁判官をして,通常人が疑いを差し挟まない程度の高度の蓋然性を基礎として確信を形成させることです。
この点,原審である東京地方裁判所は以下のとおり判断しました。 「本件鋼板において,原告が中間層と指摘する部分には,そのすべての階層部分において鉄,ニッケル及び錫が存在する(争いがない)。その代表組成は,鋼板側の領域では,おおむね鉄83原子%,ニッケル13原子%及び錫4原子%であり,さらに上層側ほど錫濃度が高くなり,もっとも錫合金層に近い側では錫50原子%程度を含有する(甲4)。これは,鉄―ニッケル合金メッキを冷延鋼板上に下地として形成した後,鉄―ニッケル―錫の合金層を生成する目的で上層に形成した錫メッキ層から,下地メッキに錫が拡散混入し,錫合金化したためであると一応推測される(甲5,弁論の全趣旨)。そうすると,本件鋼板において原告が指摘する中間層部分は,これが錫合金層と区別できる層であるか否かにかかわりなく,特許請求の範囲(i)記載の鉄メッキ,ニッケルメッキおよびクロムメッキの1種または2種以上,または鉄メッキ,ニッケルメッキおよびクロムメッキの1種または2種以上との錫メッキとの複層メッキ,若しくは鉄―錫合金メッキ,ニッケル―錫合金メッキおよびニッケル―鉄合金メッキの1種からなるものではない。したがって,本件鋼板において原告が指摘する中間層は,本件明細書の特許請求の範囲の(i)における『下地メッキ層』に該当しない。」 すなわち,原審は,本件鋼板のうち,原告が指摘する中間層の部分は,鉄―ニッケル―錫の合金であると「一応推測される」ことから,ニッケル―鉄合金メッキの1種からなるものとは認定できないと判断しており,本件鋼板の構成がどのようなものであるかについて積極的に判断しておりません。この点,読者の中には,原審が,争点であるはずの本件鋼板の構成がどのようなものであるかについて積極的に判断していないことについて疑問を抱く方もいらっしゃるかもしれません。しかしながら,一般に,特許権者敗訴の判決を下すためには,被告製品の構成を積極的に認定する必要はなく,被告製品の構成が原告主張のとおりであると認定できないと判断すれば足ります。本件の場合も,「本件鋼板において,原告が中間層と指摘する部分に存在する錫が単なる不純物であり,当該部分はニッケル―鉄の合金層からなる」とはいえないと判断できれば,原告敗訴の判決を下すことができるのです。 この考えを徹底すると,実は,原審のように,本件鋼板のうち,原告が指摘する中間層の部分が,鉄―ニッケル―錫の合金であると「一応推測される」とまであえていう必要もなく,原告が指摘する中間層の部分は,鉄―ニッケル―錫の合金である可能性が排除できないというだけでも足りるはずです。このようにいえるのであれば,原告が中間層と指摘する部分に存在する錫は,単なる不純物であり,当該部分はニッケル―鉄の合金層からなるといえることについて,通常人が疑いを差し挟まないとはいえず,その結果,裁判官は,原告が中間層と指摘する部分はニッケル―鉄の合金層からなるといえるとの確信を形成することができないからです。 |
| 3.東京高等裁判所の判断 |
|
この点,本判決は以下のとおり判断しました。
「当裁判所も,訴訟引受人(筆者注:原告の会社分割に伴い本件特許権を承継した会社)が主張する本件鋼板の中間層部分は,これをもって錫合金層と区別可能な層であると認めることができるか否にかかわりなく,特許請求の範囲(i)記載の鉄メッキ,ニッケルメッキ及びクロムメッキの1種又は2種以上,又は鉄メッキ,ニッケルメッキ及びクロムメッキの1種又は2種以上と錫メッキとの複層メッキ,若しくは鉄―錫合金メッキ,ニッケル―錫合金メッキ及びニッケル―鉄合金メッキの1種からなるものではないのであって(ここでは,「および」などの表記を公用文の方式に改めている。),原告が主張する中間層は,上記(i)における『下地メッキ層』に該当しないものと判断する。この判断を含め,訴訟引受人の本訴請求をもって理由がないとすべき認定判断は,次のとおり補充するほか,原判決事実及び理由中の『第3 争点に対する判断』に示されているとおりである(なお,原判決16頁19行目冒頭の『との』は『と』の誤記である)。 本件鋼板において訴訟引受人が主張する中間層なるものが存するか否かについて,当審においても当事者双方から詳細な主張がされている。訴訟引受人主張のこの事実を認めることができるかはさておくとしても,そもそも,訴訟引受人は,訴訟引受人主張の中間層に含まれている4原子%程度の錫がどのような形態で存在するかを確定することは,現在でもなお,実験的にも,理論的にも不可能であるとの事実を認めている(訴訟引受人第3準備書面16頁)。そうだとすると,本件鋼板において,訴訟引受人主張の中間層に上記原子%程度の錫が存している場合には,これを錫合金であることを否定できないことになり,本件鋼板はなお上記特許請求の範囲(i)記載を充足するとの証明も不可能であることに帰する。本件鋼板では,訴訟引受人主張の中間層に錫4原子%の組成があるのであるから,本件鋼板をもって特許請求の範囲(i)を充足するものと認めることはできない。」 本判決の論理は,訴訟引受人主張の中間層に含まれている4原子%程度の錫がどのような形態で存在するかを確定することは,現在でもなお,実験的にも,理論的にも不可能である以上,これを錫合金であることを否定できないことになり,本件鋼板が特許請求の範囲(i)記載を充足するとの証明も不可能であることに帰することから,本件鋼板をもって特許請求の範囲(i)を充足するものと認めることはできないというものです。この論理によると,原審のように,本件鋼板のうち,原告が指摘する中間層の部分は,鉄―ニッケル―錫の合金であると「一応推測」する必要もなくなることから,本判決の論理は,原審よりも法理論に忠実であるといえます。 本判決は,被告製品の構成の証明が不可能である場合,特許権侵害は成立しないという,法理論上は当然であるものの,実務担当者が見逃しがちな点を確認した判決として,実務上参考になると思われます。 |