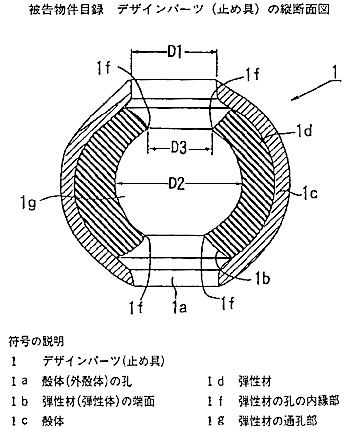
| 知的所有権判例ニュース |
| 特許権に基づく製造販売禁止等請求事件 |
|---|
| 「東京地裁 平成12(ワ)27714号,平成14年1月28日判決」 |
| 生田哲郎 山崎理恵子 |
| 1.事件の概要 |
本件は,金属製装身具ネックレス(以下,「被告製品」という)を製造及び販売している被告に対して,被告製品の製造・販売行為が原告の有する特許権を侵害するとして,その差止めと損害賠償金の支払い等を求めた事案です。
本件発明は物の発明ですが,特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されていましたので,本件発明の技術的範囲が,特許請求の範囲に記載された製造方法により製造された物に限定されるかどうかが争点になりました(争点1)。 また,特許請求の範囲に「0リング状」という文言があるところ,この文言の意義が問題となり,文言侵害,均等侵害の有無が争点になりました(争点2)。 |
| 2.本件発明 |
|
本訴訟において,原告は,被告製品が特許第3114868号の公報記載の請求項1の発明及び請求項7の発明の技術的範囲に属すると主張しました。本稿では,誌面の都合上,請求項1の発明(以下,「本件発明」といいます)のみご紹介します。
本件発明を構成要件に分説すると次のAないしFのとおりとなります。 A 外殻体と弾性体とを含む止め具であって, B 前記外殻体は,孔と中空部とを有し,前記中空部の内壁面が球面状の連続体であり, C 前記孔は,前記外殻体の外部から前記中空部へ通じており, D 前記弾性体は,通孔部を有する0リング状部材であって,前記中空部の内部に内蔵され,その外周が前記中空部の前記内壁面に圧接しており, E 前記通孔部は,前記孔に通じており, F 前記弾性体は,前記外殻体の前記孔を通って,前記外殻体の内部に導入される 止め具 |
| 3.判旨 |
|
(1) 争点1について
本件発明の構成要件Fの「前記弾性体は,前記外殻体の前記孔を通って,前記外殻体の内部に導入される」との記載は,製造方法に係る記載部分です。原告は,本件発明は物の発明であることから,発明の技術的範囲を解釈するにあたり,構成要件Fに記載された方法によって製造された物に限定すべきではないと主張しました。 裁判所は,次のように判示し,原告の主張を退けました。 「すなわち,特許発明の技術的範囲は,特許請求の範囲の記載に基づいて解釈すべきであるから,その解釈に当たって,特段の事情がない限り,明細書の特許請求の範囲の記載を意味のないものとして解釈することはできない。確かに,物の発明において,物の構造及び性質によって,発明の目的となる物を特定することができないため,物の製造方法を付加することによって特定する場合もあり得る。そして,このように,特許請求の範囲に,発明の目的を特定する付加要素として,製造方法が記載されたというような特段の事情が存在する場合には,当該発明の技術的範囲の解釈に当たり,特許請求の範囲に記載された製造方法によって製造された物に限定することが,必ずしも相当でない場合もあり得よう。本件についてこれをみると,《1》本件発明の目的物である止め具は,その製造方法を記載することによらなくとも物として特定することができ,構成要件Fは,本件発明の目的物を特定するために付加されたものとはいえないこと,《2》本件特許出願に対して,平成12年8月4日付けで,拒絶理由通知が発せられ,原告は,これを受けて,平成12年8月28日,特許庁に対して手続補正書を提出し,同補正により,構成要件Fを追加したこと等の経緯に照らすならば,構成要件Fは,本件発明の技術的範囲につき,正に限定を加えるために記載されたものであることは明らかである。したがって,本件発明の技術的範囲は,構成要件Fに記載された方法によって製造された物に限定されるというべきである。」 次に,裁判所は,構成要件Fと被告製品との対比を行いました。被告製品は,本件発明のように殻体形成後にその孔から別途形成した球形中空状弾性体を導入するのではなく,貴金属製パイプの内部に一体として嵌合された弾性材チューブが,球状のデザインパーツの殻体の形成と同時に球形中空状弾性材となって殻体内部に装着されるのであるから,構成要件Fを充足せず,本件発明の技術的範囲に含まれないと判断しました。 (2) 争点2について 本来であれば,争点1の判断のみでその余について判断することなく,直ちに請求棄却の結論を導くことも可能であったと思われますが,裁判所は,争点2についても判断しています。 (文言侵害の有無について) 構成要件Dの「0リング状」の意義について,原告は,通孔部を有するものを広く包含し,筒状のものも含まれるし,また,厚み(孔の通る方向)についての限定はないと解すべきであると主張しました。 しかしながら,裁判所は,《1》本件明細書のいずれをみても「0リング状」について,特別の意味で理解すべきとする記載箇所はないこと,《2》本件特許の出願経緯より「0リング状」は一般的な意味として解釈するのが相当であることを根拠に,構成要件Dの「0リング状」は,「円形断面の環状パッキング形状,又はこれと類似の形状」を意味し,「筒状」は含まれないと解すべきであると判断し,原告の主張を退けました。 次に,裁判所は,被告製品との対比を行い,被告製品における弾性材は,《1》殻体に内蔵されていない状態では筒状であり,《2》殻体に内蔵された状態では,球形中空状であるとして,被告製品の弾性体の形状は,円形断面の環状パッキングの形状又はこれと類似した形状ではないので,被告製品の弾性材を「0リング状」ということはできないとして,構成要件Dを文言上充足しないと判断しました。 (均等侵害の有無について) 次に,裁判所は,被告製品の弾性材が本件発明の「0リング状部材」の均等物といえるかを次のように判断しました。本件発明においては,外殻体の孔から弾性体を通すことが必要であるところ,被告製品においては,《1》殻体の成型後に,弾性材を殻体の孔から通すことが必要でないことを前提として,円柱状の弾性材を用いたものであること,《2》被告製品においては,殻体の成型後には,弾性材を殻体の孔から挿入することは不可能であることから,本件発明の構成要件Dと被告製品の構成の間には,それぞれの構成を採用するための目的,作用効果,解決のための時期,手段の選択のいずれにおいても異なるところ,構成要件Dにおける「通孔部を有する0リング状部材」を「殻体の成型前に,殻体となる貴金属製パイプの中に弾性材となる円柱状のシリコン製の弾性材チューブ」に置換することが,当業者にとって容易であるということはできないとして,被告製品の弾性材は,本件発明の0リング状の弾性体の均等物とはいえないとして,被告製品は本件発明の技術的範囲に含まれないと判断しました。 |
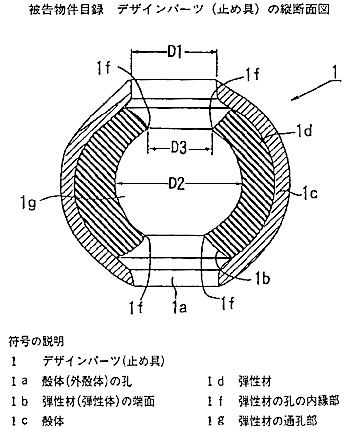
| 4.検討 |
|
物の発明において製造方法に係る記載部分がある場合における発明の技術的範囲の解釈について,本件判例は上記の一般論を判示しています。化学やバイオテクノロジーの特許発明におけるプロダクト・バイ・プロセスクレームの技術的範囲の解釈について判示したいくつかの裁判例があります(東京高裁平成7年(行ケ)第194号〔転写印刷シート事件〕,東京高裁平成6年(ネ)第2857号〔インターフェロン事件〕,最高裁平成9年(行ツ)第120号〔包装袋事件〕,東京地裁平成元年(ワ)第5663号〔ポリエチレン延伸フィラメント事件〕等)。これらの判決例は,概ね,プロダクト・バイ・プロセスクレームの特許性はプロダクト自体で判断されることから,その技術的範囲は原則として製造方法に限定されないプロダクト自体として判断されると判示しています。
本件判決に照らして考察しても,化学やバイオテクノロジーの発明のように,物の発明において,発明の目的を特定する付加要素として製造方法が記載されたというような特段の事情が存在する場合には,プロダクト・バイ・プロセスクレームの技術的範囲の解釈にあたり,特許請求の範囲に記載された製造方法によって製造された物に限定して解釈する必然性はなく,これと製造方法は異なるが物としては同一であるものも含まれると解するのが相当であるといえ,かかる結論は過去の判決例に沿うものです。 裁判所は,製造方法に係る記載部分がある物の発明の技術的範囲の解釈について上記一般論を示したうえで,本件事案については,構成要件Fの製造方法に係る記載は,本件発明の技術的範囲につき,正に限定を加えるために記載されたものであるとして,本件発明の技術的範囲は,構成要件Fに記載された方法によって製造された物に限定されると判示しました。 また,本判決は,本来であれば,構成要件Fの充足性を否定して請求棄却との結論を導けば足りるところ,構成要件Dの充足性についても判断を示しています。文言侵害の有無,均等侵害の有無についての判断は従来の裁判例の手法を踏襲していますので,参考になるでしょう。 |