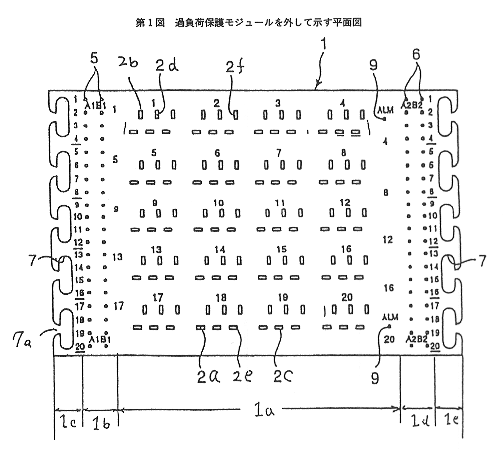
| 知的所有権判例ニュース |
| 特許権侵害差止請求事件 |
|---|
| 「平成13年5月22日 平成12年(ワ)3157号」 |
| 生田哲郎 山崎理恵子 |
| 1.事件の概要 | ||||||||||||||||||||||
本件は,電話用線路保安コネクタ配線盤装置の特許権を有する原告が被告に対し,被告が製造・販売している配線盤装置が原告の上記特許権に係る発明と均等であり,その技術的範囲に属すると主張して,上記特許権の侵害を理由とする損害賠償を求めた事案で,均等論を適用して侵害を認めた事案です。
本件発明の構成要件を分説すれば,次のとおりです。
被告製品が,上記構成要件A,B,C,D,G,J及びKを充足し,他方,構成要件E,H及びIを文言上充足しない点については,当事者間に争いがありませんでした。構成要件Fを文言上充足するかどうかについては争いがありました。具体的には,本件発明は,構成要件Eにおいて,各電線を第l及び第2の無半田電線巻付けピンに案内区別するための編み出し板を備えているが,被告製品は,編み出し板ではなく,このような案内区別するための切り欠き7aを有する整線切り欠き貫通孔7を備えており,この点で本件発明と相違しました(相違部分1)。また,本件発明は,構成要件H及びIにおいて,印刷配線板に各単位の接地用接触子が共通になるように配線パターンが形成され,印刷配線板に接地板が取り付けられ,接地板が装置を盤架に固定する手段を通じて接地するが,被告製品は,印刷配線板に各単位の接地用接触子が共通になるように配線パターン(接地用幅広肉厚パターン17)が形成され,その接地用幅広肉厚パターン17の端部から,接地用固定軸11,アース線接続圧着端子12を通じて接地しており,この点で本件発明と相違しました(相違部分2)。 |
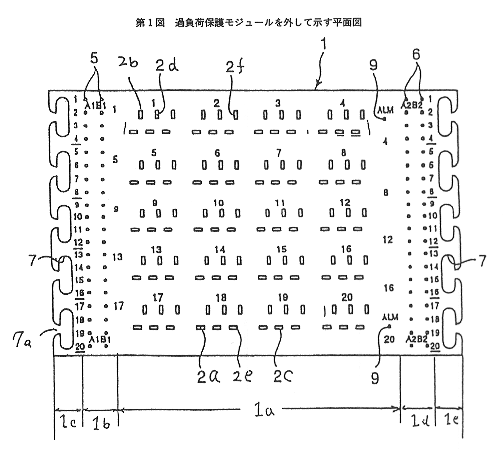
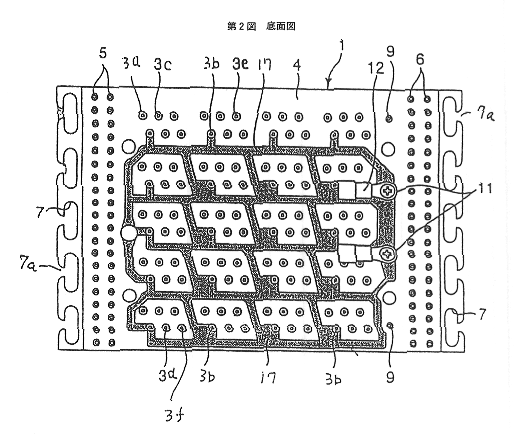
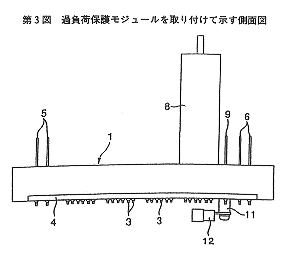
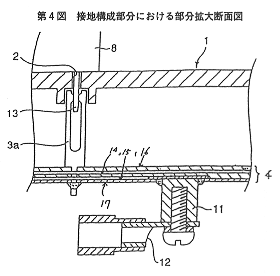
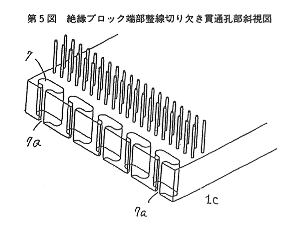
| 2・裁判所の判断 |
|
(1) 構成要件Fの充足性について,構成要件F及びHの「接地線」という用語の意味について争われました。裁判所は,「本件明細書においては,『接地線』という用語の意味について,明確に定義した記載は存しないところ,本件発明に係る技術分野においては,『接地』とは,通常,アースと同義のものであり,電気装置の一部の静電位を大地の電位と等しく保ち,また過電流が装置に入るのを避けるなどの目的で,電気装置などを大地と接続することを意味し,『接地線』とは,電気装置などを大地と接続する線路,すなわちアース線を意味する(広辞苑第5版,岩波理科学辞典第5版参照)。」と判断したうえで,このような通常の用語の意味に反して被告主張のように解することはできないとし,被告製品は構成要件Fを充足すると判断しました。
(2) 均等の成否について,裁判所は,均等論を採用した最高裁判所の判決を引用したうえで,被告製品が,本件相違部分の存在にもかかわらず,均等の5つの成立要件を満たすことにより,本件発明の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,その技術的範囲に属するものといえるかどうかについて検討を行いました。 均等の要件2(置換可能性)について,裁判所は,「本件発明は,接続子形プラグイン過負荷保護モジュールを接続する電話用線路保安コネクタ配線盤装置において,従来のものに比べて,接続構造上の無駄が省けるとともに,その接続の際に誤配線を防止し得るという作用効果を奏ずる,経済的で,正確な配線が可能な電話用線路保安コネクタ配線盤装置を提供することを目的とするものというべきである」と判断したうえで,構成要件E,H及びIにおける本件相違部分を被告製品におけるものと置き換えても,本件発明の目的を達成することができ,これと同一の作用効果を奏するものと認められ,被告製品は,均等の要件2を充足すると判断しました。 均等の要件1(相違部分が本質的部分でないこと)について,裁判所は,本件発明の本質的部分について,「本件発明は,接続子形プラグイン過負荷保護モジュールを接続する電話用線路保安コネクタ配線盤装置において,従来のものに比べて,その接続の際に誤配線を防止し得るという作用効果を達成するための手段として,それぞれの接続子形プラグイン過負荷保護モジュール及びこれと印刷配線パターンによって接続された無半田電線巻付けピンに対応するような位置に穴を設け,各電線をこの穴に通すことによって,これを巻き付けるべき無半田電線巻付けピンを容易に案内区別できるようにしたものであり,このような穴をもって各電線とこれを巻き付けるべき無半田電線巻付けピンの案内区別を容易にするという構成を採ったことが,従来技術に見られない本件発明の特徴的部分の一つであるというべきである」と判示しました。そのうえで,相違部分1が本件発明の本質的部分ではないかどうかについて,「被告製品は,過負荷保護モジュール8,無半田電線巻付けピン5,6に対応するような位置に,切り欠き7aを有する整線切り欠き貫通孔7を備えており,この貫通孔に各電線を通すことによって,各電線とこれを巻き付けるべき無半田電線巻付けピンの案内区別を容易にしているものと認められる。そうすると,本件発明の構成と被告製品の構成の相違点は,結局,穴が設けられている箇所が絶縁ブロックとは別体の,無半田電線巻付けピンに平行して取り付けられた板状の部材であるか,絶縁ブロックそのものであるかという点にあるにすぎず(被告製品において各貫通孔に設けられた切り欠きは,各電線を案内区別するための構成ではなく,配線作業を容易にするための付加的構成にすぎない。),この点を被告製品における相違部分1の構成に置き換えても,全体として本件発明の技術的思想と別個のものと評価されるものではない。したがって,相違部分1は,本件発明の本質的部分ではないというべきである」と判断しました。 次に,相違部分2が本件発明の本質的部分ではないかどうかについて,「構成要件H及びIにおける「接地板」,「盤架」及び「固定する手段」の構成は,これを被告製品における相違部分2の構成に置き換えても,単に接地の経路が変更されるだけであり,本件発明の作用効果との関連において,全体として本件発明の技術的思想と別個のものと評価されるものではない」として,相違部分2は,本件発明の本質的部分ではないと判断しました。 均等の要件3(容易想到性)について,裁判所は,被告製品の製造時において,当業者は,本件相違部分を被告製品におけるものと置き換えることに,容易に想到することができたというべきであり,被告製品は,均等の要件3を充足すると判断しました。 均等の要件4及び5における均等の成立を妨げる事情については,被告が具体的な事情を主張して争わなかったとして,被告製品は,これらの均等の要件を充足すると判断しました。 以上より,裁判所は,被告製品は,本件発明の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,その技術的範囲に属すると判断し,原告の損害賠償請求の一部を認めました。 |
| 3.検討 |
|
わが国において均等論について初めて実質的な判断を示したボールスプライン事件最高裁判決(最高裁平成6年(オ)第1083号同10年2月24日第三小法廷判決)以後に均等を認めた事例としては,本判決のほかに,注射方法及び注射装置に関する大阪地裁の判決(平成8年(ワ)第12220号判決),海苔異物除去機に関する東京高裁の判決(平成12年(ネ)第2147号)があります。
本判決は新たな判断を示したものではありませんが,均等論適用を肯定した一事例として紹介します。 均等の要件として,(1)相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと,(2)作用効果の同一性,(3)侵害時における置換容易性,(4)対象製品が出願時の公知技術から容易推考できたものではないこと,(5)出願経過禁反言などの特段の事情のないこと―の5つが掲げられています。この5つの要件のうち,(1)の要件の意味を巡っては議論があったところ,本判決は,「発明が各構成要件の有機的な結合により特定の作用効果を奏するものであることに照らせば,対象製品との相違が特許発明における本質的部分に係るものであるかどうかを判断するに当たっては,単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく,特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で,対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか,それともこれとは異なる原理に属するものかという点から,判断すべきものというべきである」と判示し,技術思想の同一性または解決原理の同一性と同じ趣旨であることを明らかにしました。 本判決は,積極的要件(1)ないし(3)は均等を主張する者が,(4)及び(5)は均等を否定する者がそれぞれ証明責任を負担すべきであるという前提のうえで,各要件を順次検討しています。 なお,出願時に置換容易なものには均等論は適用すべきではないとの見解があります。本事案においでは,相違部分が侵害時のみならず,出願時においても置換容易なものでしたが,被告はこの点について特に争わず,判決においても結果として均等論を適用しでいます。 また,本判決においては,均等の要件の適用にばかり目を奪われがちですが,特許請求の範囲において用いられる用語の意味について,当該発明に係る技術分野における通常の意味を参酌して解釈を行うという従来からの手法を用いている点でも参考になります。 |