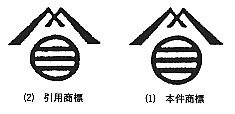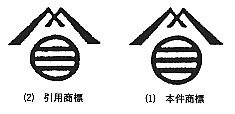
| 知的所有権判例ニュース |
| 一地域で長年使用されてきた商標が出所表示性を 欠いていると判断された事例 |
|---|
| 「東京高等裁判所平成12年3月16日判決」 |
| 水谷直樹 |
| 1.事件の内容 |
被告長野県製薬(株)は,指定商品を旧第1類「もぐさ,その他本類に属する商品」とする後記登録商標(本件商標)を有していたところ,原告日野製薬(株)は,本件商標は,原告が長年の間使用してきた後記引用商標(引用商標)と同一であるから,商標法4条1項10号等に違反するとして,平成5年に特許庁に無効審判請求を申し立てました。しかし,特許庁では,平成9年に審判請求は成り立たない旨の審決がなされました。
そこで,原告は上記審決の取消しを求めて,平成9年に東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起しました。 |
| 2.争 点 |
|
本事件の争点は,原告の主張のとおり,本件商標が商標法4条1項10号に違反しているのか否かとの点でした。
|
| 3.裁判所の判断 |
|
東京高等裁判所は,平成12年3月16日に判決を言い渡しましたが,上記争点について,
「確かに≪証拠略≫を総合すれば,引用商標は, その使用開始の時期は必ずしも明らかでないものの,少なくとも,本件商標の登録出願前の何十年にもわたって,原告の前身である日野製薬合名会社あるいは原告が製造販売した大量の生薬の包装に使用され,また,全国的な,あるいは長野県全域にわたる媒体によるものを含む,その種々の宣伝・広告にも使用されてきたことを認めることができ,このような事実の下では引用商標が,本件商標の登録出願前に,原告によって使用されるものとして,広く知られていたと認める余地は十分にあるというべきである。」 「しかしながら,原告によって使用されるものとして知られることと,原告の製品であることを示すものとして知られることは別のことであり,以下の諸状況を考慮すると,仮に,引用商標が,本件商標の登録出願前,原告によって使用されるものとして取引者・需要者によく知られるに至っていたとしても, それが,商品の出所を示すものとして,すなわち,それの付された商品が原告の製造・販売に係る商品であることを示すものとして,取引者・需要者に認識されていたものと認めることはできないというほかない。」 「≪証拠略≫によれば,原告自身,本件標章は,特定の者によって,独占されるべきものではないと考えて,すなわち,木曽地域の者,皆によって使用されてきたものであり,そのように使用されるべきであると考えて,使用してきていたことが認められる。」 「本件商標の登録出願当時,本件標章は,原告が製造・販売する生薬にも長年にわたって使用されてきたものであると同時に,被告が製造・販売する生薬にも原告が使用を開始するよりも更に古くから長年にわたって使用されてきたものであったことが明らかである。 他方,このように木曽地域という同一の地域で同一の種類の事業を営む原告及び被告によって同一の標章(本件標章)が同一あるいは類似の商品に長年にわたって大量に使用されてきているにもかかわらず,その間,本件訴訟に至るまで,本件標章の使用に由来する出所の混同等の問題が生じた形跡は,本件全証拠を検討しても見出すことができない。この事実は,他により確実で合理的な説明が可能でない限り,本件標章には,本来,出所表示機能が備わっていないことを根拠づけるものというべきである。より具体的にいえば,本件標章は,木曽地域で製造される木曽御岳神社にゆかりのある生薬という商品自体を示すものとしての機能を有するものであって,特定の人とのつながりにおいて認識されるものではない,ということである。」 「本件標章には,その使用が古くは江戸時代に始まって以来,被告と原告とが共に使用してきた期間を含め,本件商標の登録出願に至るまでの間の少なくとも大部分の期間,一人の者によってではなく,木曽地域に根拠を置く複数の者によって,そこで製造される生薬に同時に使用されてきたという歴史があるということができる。・・・・・・本件標章に,それの付された商品の出所(人)というより,木曽地域で製造される木曽御岳神社にゆかりのある生薬という商品自体を示すものとしての機能を与える働きを有するものというべきである。」 と判断して,商標法4条1項10号違反の事実は存在しないとして,原告の請求を棄却しました。 |
| 4.検 討 |
|
本判決は,上記引用のとおり,本商標は,古くから木曽地域において生産されてきた生薬という商品そのものを示す機能を果たしてきたと認定したうえで,本商標には特定の者の製造,販売に係る商品であるという出所表示機能が備わっていないと認定しています。
原告は,本商標は原告の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間で広く知られていた(周知)と主張していましたので,上記認定の事実を前提とする限り,そのような主張が裁判所で認められることは困難と思われ,請求棄却もやむを得ないものと考えられます。 他方で,上記事実認定を前提とする限り,本商標は出所表示機能を欠くということになると思われますので,商標法4条1項10号ではなく,同法3条1項2号(慣用商標)を根拠にすれば,無効となる余地もあったように思われます。 もっとも,商標法4条1項10号の適用を前提とする場合には,原告は,本商標登録を無効としたうえで,自ら商標登録を得ることが可能と思われますが,商標法3条1項2号の適用を前提とする限りは,誰も商標登録を得ることができないことになりますので,この点で相違点が生じてくることになります。 いずれにしても,本事件は,特殊な事実関係を前提にしてはいるものの,商標の基本(出所表示性)を考えるうえで,大変興味深い事案であると思われます。 |