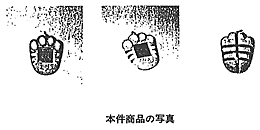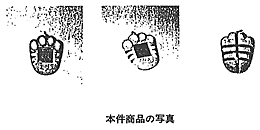
| 知的所有権判例ニュース |
| 複数当事者が新製品の商品化にあたり費用,役割 を分担した場合に,当該製品は,上記当事者間で は,不正競争防止法2条1項3号所定の「他人の 商品」には,相互に該当しないと認められた事例 |
|---|
| 「東京地方裁判所平成12年7月12日判決」 |
| 水谷直樹 |
| 1.事件の内容 |
原告(株)ナコインターナショナルは,猫の掌の形をした携帯用ゲーム機を発案したと主張しています。
他方で,被告(有)ブルブルほか2名は,上記猫の掌の形の携帯用ゲーム機を,原告に対して10万個を発注するとともに(本件第一商品),原告が実質的に同一のゲーム機であると主張している携帯用ゲーム機を,香港の企業に対しても別途発注し,我が国に輸入して販売していました。 そこで,原告は,被告らに対して,被告らが香港の企業に発注して,日本国内で販売した携帯用ゲーム機は,不正競争防止法2条1項3号(形態模倣)に該当する商品であると主張して,被告らに対して,被告らの上記販売行為により原告が受けた損害賠償の支払いを求め,平成10年に,東京地万裁判所に訴訟を提起しました。 |
| 2.争点 |
|
同事件の争点は,被告らが,原告に対して発注した携帯用ゲーム機は,被告らにとって,不正競争防止法2条1項3号所定の「他人の商品」に該当するのか否かとの点でした。
|
| 3.裁判所の判断 |
|
東京地方裁判所は,平成12年7月12日に判決を言い渡しましたが,同判決中で,上記争点について,
「不正競争防止法2条1項3号は,『他人の商品』の形態を模倣した商品を譲渡,貸し渡し,輸入する行為等につき不正競争行為とする旨規定する。右規定が設けられた趣旨は,費用,労力を投下して,商品を開発して市場に置いた者が,費用,労力を回収するに必要な期間の間(最初に販売された日から3年),投下した費用の回収を容易にし,商品化への誘因を高めるために,費用,労力を投下することなく商品の形態を模倣する行為を規制することとしたものである。したがって,同号の保護を受けるべき者に当たるか否かは,当該商品を商品化して,市場に置くに際し,費用や労力を投下した者といえるか否かを吟味することによって決すべきことになる。仮に,甲,乙それぞれが,当該商品を商品化して市場に置くために,費用や労力を分担した場合には,第三者の模倣行為に対しては,両者とも保護を受けることができる立場にあることはいうまでもない。しかし,甲,乙間においては,当該商品が相互に『他人の商品』に当たらないため,当該商品を販売等する行為を不正競争行為ということはできない。」 「右のとおり,①本件第一商品の商品化の過程をみると,確かに,ゲームのシナリオを作成し,ゲーム機の外観を猫の掌の形状にするとの着想を提示したのは原告であるが,その後本件第一商品の外観デザイン,名称,パッケージデザイン及び取扱説明書を作成したのは被告らであり,その後も試作品を作成する過程においても,被告らが,細部にわたり詳細な指示を与えていたこと,②ゲーム機において,その外観のデザイン,パッケージデザイン,商品の名称は消費者の購買意欲に影響を与え,商品化における重要な要素であるが,内容,形状の最終的な決定は被告らが行ったこと,③本件において,新規商品である本件第一商品10万個を市場に流通させ,これを販売することによって費用の回収を図ることができるか否かのリスクを専ら負担しているのは,被告らであったといえること等の事実に照らすならば,被告らは,本件第一商品の商品化に当たり,費用及び労力を投下して,その制作に関与した者と解するのが相当である。 なお,原告は,ゲームとしてのストーリーや猫の掌を模した形態が原告の発案によるものであることを理由に,本件第一商品は,専ら原告の商品に当たる旨を主張する。しかし,同項3号は,その開発者を模倣者との関係で保護しようとするものであって,そのアイデア自体を保護する趣旨の規定ではないこと,本件第一商品の商品化にあたっての被告らの関与の程度が前記のとおりであることに照らし,右原告の主張は採用できない。 そうすると,被告らにとって,本件第一商品は『他人の商品』に該当せず,被告らの行為は,不正競争防止法2条1項3号の定める不正競争行為には該当しない。」 と判示して,原告の請求を棄却しました。 |
| 4.検討 |
|
本事件では,不正競争防止法2条1項3号が規定している形態模倣の有無が争われました。
本事件で実質的に争われた点は,他の同種の事件とは異なり,原告が形態を模倣されたと主張している製品が,被告らにとって「他人の商品」といえるのか否かとの点でした。 本事件では,形態模倣が問題となった製品の開発に,被告らも関与していたために,このような場合にも,上記製品は,被告らにとって「他人の商品」であるといえるのか否かが問題とされたものです。 一般に,ある商品の開発に複数の者が関与している場合に,その商品が,いずれの者の商品であるといえるのかは,個別の認定の問題ではありますが,これが自己の商品でもあると認定された場合には,当該製品は,不正競争防止法2条1項3号所定の「他人の商品」に該当しないこととなり,これを自ら製造したとしても,同号所定の形態模倣の問題は生じてこないものと考えられます。 本事件で裁判所は,上記引用のとおり認定することにより,問題となった商品は,被告らの商品でもあると認定して,原告の請求を棄却しました。 今後は,この問題に関しては,複数の者が商品開発に関与した場合に,商品開発への関与の程度により,どのような場合であれば自己の商品であると認定され,どのような場合であれば,これが否定されるのかが問題となってくることと思われます。 企業が新製品の開発を行う際に,外部企業の協力を得ることは,しばしば行われていることですが,この場合に,開発された製品が,不正競争防止法2条1項3号を適用するうえで,誰の商品といえるのかという観点から,この問題を考えてみると興味深いものがあるように思われます。 |