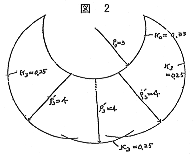原告Xは,名称を「脇下汗吸収パッド」とする考案について,登録を受けていました。この考案は,その名称の通り,衣服の脇の下の部分に取り付けて,汗を吸収するパッドの吸収効率を良くするものです。その要旨を簡単に述べます。従来三日月形のパッドが存在しましたが,三日月形をしていると両端の部分が幅が狭く,汗を吸収する能力に欠けます。そこで,一定幅の円弧状にすることも考えられますが,それでは美観が良くありません。そこで下図1の袖と身頃の境目に当てる部分4(判決では「湾曲連結部」と呼ばれています)の曲率半径より小さい曲率半径で3つの円弧を描いて,他方の外縁を形成する,とするものです。
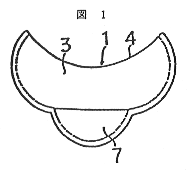
こうすれば,汗吸収能力が大きく,かつ外縁が花びらのような形になってデザインが良くなります。しかるに原告Xは,上記「曲率半径」と記載すべきところを,「曲率」と記載してしまったのです。
Xはこの考案について,訂正審判を請求し,曲率が小さいと記載したのでは,曲率半径が大きいと誤解させる虞れがある,と述べて,「明瞭でない記載の釈明」を目的とし,「曲率」を「曲率半径」と訂正することを申し立てました。この訂正審判請求は認められ,その訂正審決は確定しました。
これに対して,被告Yは訂正無効審判を請求し,曲率が小さいとは曲率半径が大きいという意味であり,これを曲率半径が小さい,と訂正するのでは,意味が反対になり,要旨の変更に当たると主張しました。特許庁はこの主張を認め,次のように述べて,訂正無効の審決をしました。「三日月形のパッドに対して汗吸収性を向上する構成は,両端部に汗吸収性を向上させる吸収面幅が形成される湾曲状に広がった部分を有すればよいことが理解され,該湾曲の形状は,湾曲連結部の曲率に対して大きい場合でも小さい場合でも前記吸収面幅を大きく取るための設計は可能である」「『曲率の小さい』の用語は技術的意味が明瞭であり,その概念が『曲率半径の小さい』とは逆の意味であることも明らかである」「『曲率の小さな』とあるのを『曲率半径の小さな』と訂正することは,明瞭でない記載の釈明を目的とするものとはいえないから,本件訂正は実用新案法39条1項3号の規定に該当しない」
これに対してXは審決取消訴訟を提起し,「曲率」と「曲率半径」とでは意味が逆になることは認めながらも,これは錯誤による誤記であるから,やはり訂正は有効である,と主張しました。これに対して被告Yは,「誤記」というのは,単なるタイプミスのように,その記載自体から明らかな書き誤りをいうのであって,出願人の無知あるいは誤解に基づく間違いはこれに含まれない,と主張しました。
Xはこの考案について,訂正審判を請求し,曲率が小さいと記載したのでは,曲率半径が大きいと誤解させる虞れがある,と述べて,「明瞭でない記載の釈明」を目的とし,「曲率」を「曲率半径」と訂正することを申し立てました。この訂正審判請求は認められ,その訂正審決は確定しました。
これに対して,被告Yは訂正無効審判を請求し,曲率が小さいとは曲率半径が大きいという意味であり,これを曲率半径が小さい,と訂正するのでは,意味が反対になり,要旨の変更に当たると主張しました。特許庁はこの主張を認め,次のように述べて,訂正無効の審決をしました。「三日月形のパッドに対して汗吸収性を向上する構成は,両端部に汗吸収性を向上させる吸収面幅が形成される湾曲状に広がった部分を有すればよいことが理解され,該湾曲の形状は,湾曲連結部の曲率に対して大きい場合でも小さい場合でも前記吸収面幅を大きく取るための設計は可能である」「『曲率の小さい』の用語は技術的意味が明瞭であり,その概念が『曲率半径の小さい』とは逆の意味であることも明らかである」「『曲率の小さな』とあるのを『曲率半径の小さな』と訂正することは,明瞭でない記載の釈明を目的とするものとはいえないから,本件訂正は実用新案法39条1項3号の規定に該当しない」
これに対してXは審決取消訴訟を提起し,「曲率」と「曲率半径」とでは意味が逆になることは認めながらも,これは錯誤による誤記であるから,やはり訂正は有効である,と主張しました。これに対して被告Yは,「誤記」というのは,単なるタイプミスのように,その記載自体から明らかな書き誤りをいうのであって,出願人の無知あるいは誤解に基づく間違いはこれに含まれない,と主張しました。