特許請求の範囲において,特定の量に数値を限定した発明は沢山あります。このような数値限定発明については,その限定数値について,常に臨界性(その数値を境にして,急激に結果の差異が生ずること)を要求する,とする見解があります。しかしその見解は,正しいとは思えません。なぜそのような数値限定がなされたかによって,臨界性が要求される場合と,されない場合があると考えます。判例にも,臨界性が要求されるとする場合と,されないとする場合とがあります。
先ず,その発明について,数値限界をしなければ,単に公知の発明の一態様にすぎず,そこに何ら進歩性が認められない場合には,数値限定をして初めて特許性が認められるのであり,臨界性が要求されるというべきでしよう。公知発明においても,その発明を実際に実施するに当たっては,関係する各種の「量」について何らかの具体的数値を選択せざるを得ません。したがって,その「量」について,単に数値を選択したからと言って,特許性が発生するものではありません。この場合には,その特定の数値を限定したことによる特段の効果が認めなければならない筈です。
一方,その様な数値限定をしなくても,特許性(具体的に言えば,新規性と進歩性)が存する発明があります。特別に「量」に関係なく,有用な効果をもたらす新規な組み合わせを発明した場合には,当然に特許性が認められるべき筋合いのものです。ただ,単に「組み合わせた」と言っても,その具体的な量の記載がなくては,発明の趣旨を理解することができない場合があります。例えば,AとBを組み合わせることにより,新たな効用が得られたとしても,構成の一つであるBがいくら少なくても(ほとんどゼロでも)良いとすることはできません。したがって,その量の程度を示すことは発明を具体的に示す上において,やはり一定の意味があるのです。その様な意味で数値を持って構成を具体的に示す場合には,数値の限定をしたことに発明性があるのではありませんから,その数値に臨界的意味がなくても良いのです。
本件においては,数値限定をすることによって特許性が出てきた場合ですが,問題の第2表を基にグラフを描けば,下図の様になります。
先ず,その発明について,数値限界をしなければ,単に公知の発明の一態様にすぎず,そこに何ら進歩性が認められない場合には,数値限定をして初めて特許性が認められるのであり,臨界性が要求されるというべきでしよう。公知発明においても,その発明を実際に実施するに当たっては,関係する各種の「量」について何らかの具体的数値を選択せざるを得ません。したがって,その「量」について,単に数値を選択したからと言って,特許性が発生するものではありません。この場合には,その特定の数値を限定したことによる特段の効果が認めなければならない筈です。
一方,その様な数値限定をしなくても,特許性(具体的に言えば,新規性と進歩性)が存する発明があります。特別に「量」に関係なく,有用な効果をもたらす新規な組み合わせを発明した場合には,当然に特許性が認められるべき筋合いのものです。ただ,単に「組み合わせた」と言っても,その具体的な量の記載がなくては,発明の趣旨を理解することができない場合があります。例えば,AとBを組み合わせることにより,新たな効用が得られたとしても,構成の一つであるBがいくら少なくても(ほとんどゼロでも)良いとすることはできません。したがって,その量の程度を示すことは発明を具体的に示す上において,やはり一定の意味があるのです。その様な意味で数値を持って構成を具体的に示す場合には,数値の限定をしたことに発明性があるのではありませんから,その数値に臨界的意味がなくても良いのです。
本件においては,数値限定をすることによって特許性が出てきた場合ですが,問題の第2表を基にグラフを描けば,下図の様になります。
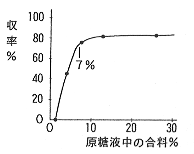
このような顕著な場合は,判決が判示する通り臨界性を認めるべきであったのであり,判決は妥当だと考えます。この数値の臨界性を特許庁が看過したのは,肯けません。