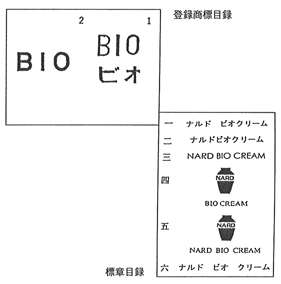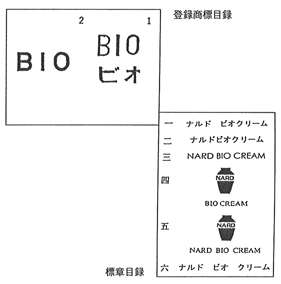
| 知的所有権判例ニュース |
| 商標の類否等が争われた事例 |
|---|
| [東京地方裁判所平成9年10月20日付判決] |
| 水谷 直樹 |
| 1.事件の内容 |
原告鐘紡(株)は,後記登録商標目録1,2記載の登録商標(指定商品=化粧品および香料)2件(以下あわせて「本件商標」と呼ぶこととします)を有していたところ,被告(株)自然化粧医学会は,その販売する化粧品,容器,包装,広告物等に,後記標章目録一ないし六記載の標章を使用しておりました。
そこで,原告は,被告に対して,被告による上記標章の使用は,原告の本件商標に関する商標権を侵害するとして,被告による上記標章の使用の差止めおよび商標使用料相当の損害賠償の支払いを求めて,平成7年に東京地方裁判所に訴訟を提起いたしました。 |
| 2.争点 |
|
① 原告の本件商標と被告標章は相互に類似しているか
② 仮に原告の本件商標と被告の標章との間の類似性が認められた場合において,商標使用料相当の損害額の具体的金額いかん |
| 3.判決 |
|
東京地方裁判所は,平成9年10月20日に判決を言い渡しましたが,まず,上記①の争点については,
「本件第一商標は,・・・上段に欧文字で『BIO』と横書きされ,下段に片仮名で『ビオ』と横書きされたものであり,本件第二商標は,・・・欧文字で『BIO』と横書きされたもので,いずれも『ビオ』なる称呼を生ずるものである」 「原告が昭和三三年以降『BIO』なる標章を化粧品に付して販売していたこと,その後新シリーズとして販売開始されたBIOシリーズは,わが国化粧品業界の大手である原告の豊富な品種を擁する化粧品シリーズであり,原告の主力商品シリーズの一つとして,一○年以上の間,広く宣伝され,かつ大量に販売されてきたものであることからすれば,『BIO』の標章は,原告の化粧品シリーズを表示するものとして,化粧品の取引者・需要者の間で周知であり,その標章自体が化粧品の分野において,強い商品識別力をもつものといえ,さらには,『BIO』と称呼を同一にする『ビオ』の標章にも,やはり化粧品の分野において強い商品識別力があるものといえる。」 「以上のような諸事情を考慮すると,本件化粧品に使用された被告標章一に接した取引者・需要者としては,商品の性状を表すにすぎない『クリーム』の部分や,特定の一般的な観念を生じさせない,なじみの薄い『ナルド』の部分よりも,前記のとおり,化粧品の分野において強い商品識別力を有する『ビオ』の部分に特に注目して取引することもあり,その結果,『ビオ』と称呼して取引することもあるというべきである。 したがって,被告標章一と本件商標とは,少なくとも称呼において同一であるから,その結果,被告標章一は本件商標に類似するものと認められる。」 と判示して,原告の本件商標と被告標章一との間の類似性を認め,その他の標章二ないし六についても,同様の理由により,本件商標との間の類似性を認めました。 判決は,上記判断を前提として,上記争点②について, 「外国からの技術導入に当たっての実施料率データを技術分野別に収集した社団法人発明協会発行の『実施料率(第四版)』によれば,・・・商標のみの許諾例で実施料率八パーセントを超える例は,右合計三五二例中,四件である。他方,その他の分野では,商標権の実施料率が一○パーセントを超える例が数件存在し,実施料率は年々上昇する傾向にある。」 「原告は,重要な商標権について第三者に使用許諾した実例はなく,侵害行為を発見した場合,一○○万円ないし二○○万円の支払いを受けて若干の猶予期間使用を許諾した何があり,また,それほど重要でない商標については,使用商品の販売額に関係なく,年間五○万円程度の使用料の支払いを受けて使用許諾した例がある。」 「右認定の事実に,本件商標が化粧品の分野において周知な商標であり,本件商標を付したBIOシリーズが原告の主力商品の一つをなしていること及び被告の侵害行為の態様その他本件にあらわれた一切の事情を総合考慮すれば,本件商標の使用に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額は,一○○万円(一年当たり二○万円,争いのない販売額の約八パーセント)と認めるのが相当である。」 と判示して,結論として原告から被告に対する被害標章の使用の差止請求を認め,また損害賠償の請求についても,上記のとおり,その請求を認めました。 |
| 4.検討 |
|
本事件は,商標侵害の有無をめぐる訴訟であり,本件商標と被告標章の類否が問題となりました。
本判決は,被告標章である“ナルドビオクリーム”について,上記で引用した理由を示して,この被告標章のうち“ビオ”の部分が取引者,需要者の注目を,もっとも集めやすい部分であると認定したうえで,本件商標と被告標章との間の類似性を肯定いたしました。 上記判断は,判決が認定した事実を前提とする限りは,オーソドックな判断であり,相当であると考えられます。 次に,判決は,被告が支払うべき商標使用料相当の損害額について,販売額の8%が相当であると認定しております。 本判決の事実認定によれば,本件商標は,原告が長年使用してきているものであり,本件商標を付した化粧品が大暈に販売されてきたこと,継続して広告,宣伝がなされてきたこと等の結果として,周知性を獲得するに至っていると認定されております。 上記事実認定を前提としたうえで,被告の標章が,このような周知商標に類似する標章であると認められた以上は,商標使用料として,販売額の8%程度の支払いを命じられたとしても,これはやむを得ないことではないかと考えられます。 本判決は,この点においても相当であると考えられます。 |