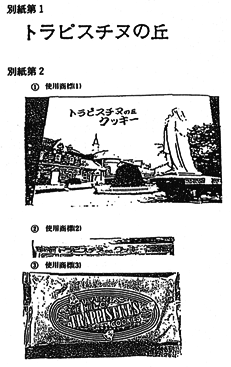
| 知的所有権判例ニュース |
| 商標の不正使用による取消審判請求が 認められた事例 |
|---|
| 〔東京高等裁判所平成8年7月18日付判決〕 |
| 水谷直樹 |
| 1.事件の内容 |
原告昭和製菓(株),函館で「トラピスチヌの丘クッキー」を製造,販売しているところ,第1の登録商標「トラピスチヌの丘」(本件商標―指定商品:キャンディ,その他の菓子,を有しており,これを第2のとおりの態様で使用しておりました(使用商標(1)〜(3))。
被告天使の聖母トラピスチヌ修道院は,同じく函館で昭和17年ころから,「トラピスチヌクッキー」,「トラピスチヌバター飴」等を製造,販売しており,「トラピスチヌ」,「トラピスチヌバター飴」等の登録商標を有しておりました。 被告は,原告に対して,昭和61年,商標法51条に基づき,特許庁に本件商標の取消審判を請求したところ,特許庁がこれを認容したため,原告が,平成6年に,この審決の取消しを求めて東京高等裁判所に提訴いたしました。 |
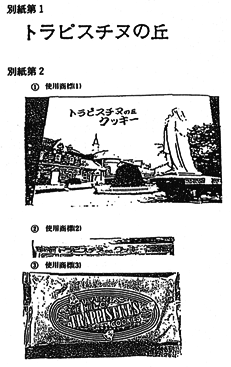
| 2.争点 |
|
商標法51条は「商標権者が,故意に,指定商品についての登録商標に類似する商標の使用,又は指定商品に類似する商品についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であって,商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたときは,何人も,その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる」と規定しているため,本事件での争点は,
(1)本件商標と原告が実際に使用している商標は同一であるか,または類似しているか (2)原告の上記商標の使用により他人の業務との間で混同が生じているか (3)原告の故意の有無 でした。 |
| 3.裁判所の判断 |
|
東京高等裁判所は,平成8年7月18日に判決を言い渡しましたが,上記(1)の争点につき『本件商標と使用商標(1)及び(2)とを比較検討するならば,両者は,いずれも,「トラピスチヌノオカ」という同一の称呼及び「トラピスチヌの丘」としての同一の観念を生じるものと認められる。
しかしながら,外観において,本件商標は,同一の大きさの「トラピスチヌの丘」の8文字を横書きしてなるものであるのに対し,使用商標(1)は,聖女像を右側約3分の1に配したトラピスチヌ修道院の図形を背景として「トラピスチヌの丘」の8文字を横書きしてなり,使用商標(2)は,「トラピスチヌの丘」の8文字を横書きしてなるものであるが,いずれも,そのうちの「の丘」の部分が「トラピスチヌ」の文字部分に比べて小さく表示され(使用商標(1)においては約2分の1,使用商標(2)においては約3分の1),「トラピスチヌ」の文字部分が,取引者,需要者注意を引く構成とされているものというべきである。 そうすると,使用商標(1)及び(2)と本件商標は,その称呼,観念を共通にするものの,外観において異なるものといわざるをえないから,使用商標(1)及び(2)は,本件商標と同一の商標と認めることはできず,本件商標に類似する商標というべきである。』 と判断し,使用商標(3)についても同様に判断したうえで,上記争点(2)につき, 『原告の使用商標を付した商品(クッキー)は,昭和53年におけるその発売の当初から,特に「トラピスチヌ」「TRAPPISTINES」の文字部分の強調により,一般の取引者,需要者に対し,一見,被告により製造,販売されているものの一つであるかのような誤解を与えかねないものの一つであるといわざるをえず,そうすると,原告による使用商標の使用は,一般の取引者,需要者に対し,被告の販売に係る商品との出所の混同を生じさせるおそれが十分にあるものというべきである。』 と判断し,最後に上記(3)の争点につき, 『原告は,昭和42年,被告と同じ函館市内において,菓子の製造,卸,小売等を目的として設立された会社であり,・・・・・・そのことに,・・・・・・被告が,その所在地において,長年に渡り「トラピスチヌ」及び「TRAPPISTINES」を要部とする商標を付して「クッキー」等を製造,販売してきたこと,また,被告における上記製造,販売の事実が一般に知られたものであること等を合わせ考慮するならば,原告は,使用商標を使用して「クッキー」の販売を開始した当時において,被告による上記「トラピスチヌ」及び「TRAPPISTINES」の商標を付した商品の事実を当然に知っていたものというべきであり,・・・・・・原告は,本件商標の指定商品(菓子)の一種である「クッキー」について,使用商標を使用するにあたり,被告の業務に係る商品と混同を生じさせることを当然に認識していたものと認めるのが相当である。』 と判断して,特許庁の審決を維持し,原告の請求を棄却いたしました。 |
| 4.検討 |
|
商標法51条(不正使用による商標登録の取消審判)は比較的なじみのない条文とも言えますが,同審判制度の趣旨については,一般には,商標権者は指定商品について登録商標を使用する権利があるが(使用権),登録商標に類似する商標の使用等(禁止権の範囲)は,権利として使用できるものではなく,事実上自由に使用できるにとどまるから,この範囲において不正使用を行った場合には,公益の見地から商標登録取消の制限を加え,これにより需要者を保護するものと説明されております(類似の制度として商標法53条を参照してください)。
このため取消審判請求は何人も行えることを原則としますが,本件では利害関係人である被告から審判請求がなされております。 本判決では,原審決の判断を支持しておりますが,個々の争点に対する判断は,いずれも妥当なものと考えられます。 なお,本取消審判制度は,例えば商標未登録の有名外国ブランドにつき,国内の第三者が,無断で商標登録をし,その類似商標を使用している場合等には,利用可能な制度とも言えそうです。 |