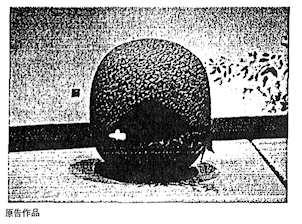
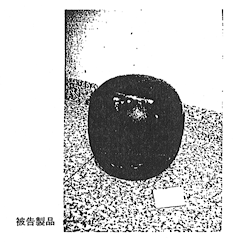
| 知的所有権判例ニュース |
| 著作物の表現とアイディアの区別につき判断を示した事例 |
|---|
| 水谷直樹 |
| 1.事件の内容 |
原告村澤明生氏は,昭和62年頃,自然石ないし石様の外観を有する容器であって,明かり窓を開け,内部を空洞とし,これに水をたたえて,水面上に蝋燭の明かりを灯すとの内容の作品を,2種類作成いたしました。
これに対して,被告(株)たち吉は,平成4年に同種の容器(2種類)の製造,販売を開始いたしました。 そこで,原告は,被告の行為は,原告の上記作品の著作権を侵害するものであるとして,平成6年に,被告製品の製造,販売の差止及び損害賠償を求めて,京都地方裁判所に訴訟を提起いたしました。 |
| 2.争点 |
|
同事件での争点は,
①原告の各作品に著作物性が認められるか ②被告製品(イ号,ロ号)は,原告の著作権を侵害しているか否か でした。 |
| 3.裁判所の判断 |
|
京都地方裁判所は,平成7年10月19日に判決を言い渡し,まず①の争点について,
「被告は,本件各作品は,古来から存在する『火もらい』に類似しているから著作物性がない旨主張するが,本件における全証拠を子細に検討しても,本件各作品と同一の作品が過去に存在したことを認めることはできず,また,本件各作品は,右1ないし3のとおりの構成により『アンコウ』というタイトルに連想されるような神秘的・幻想的な空間を表現しようとするものであって,著作者の思想又は感情を創作的に表現しているものと認めることができる」と判示して著作物性を認めました。 次に,②の争点について,判決は,「著作権ないし著作者人格権に対する侵害の有無は,原作品における表現形式上の本質的な特徴自体を直接感得することができるか否かにより決められなければならない。」, 「①著作物が思想又は感情を創作的に表現したものであって,同一人による著作物であっても個々の著作物により別々にその表現は異なるものであり,著作者の思想ないし感情は,いわばその著作物の個性に具現されていると考えられること,②著作権の享有にいかなる方式の履行も要しないことを考えると,前項にいう『表現形式上の本質的特徴』は,それぞれの著作物の具体的な構成と結びついた表現形態から直接把握される部分に限られ,個々の構成・素材を取り上げたアイディアや,構成・素材の単なる組み合わせから生ずるイメージ,著作者の一連の作品に共通する構成・素材・イメージ(いわゆる作風)などの抽象的な部分までは及ばないと解するべきである。」と判示し,「(本件作品一と)イ号作品,ロ号作品との共通点といえば,明かり窓を穿ち,容器内部に水を浮かべて浮き蝋燭の明かりを灯しうることとなっている点であるが,・・・・・・イ号作品,ロ号作品とも,外観は一見して陶器とわかるものであり,明かり窓もイ号作品は『松』を象り,ロ号作品は容器上部の半分を切り取るような形状の口であって,たとえ,内部に水を満たして浮き蝋燭を灯したとしても,前記のような本件作品一の本質的特徴部分を直接感得できるものと認めることはできない。」と判示し,更に,原告の本件作品ニとイ号,ロ号製品との対比についても同様に判示したうえで,「原告は,原告の著作物の表現形式上の本質的な特徴は,いわゆる従来の『火もらい』とは異なるデザイン重視の容器を製作し,さらにその容器内部に液体を満たして,その表面上に発光体を浮かべて,一体のものとして幽玄な空間を表現している点に存する旨主張するが,こうした点は個々の著作物を離れた抽象的なアイデアに属するものであり,右の点の類似のみを理由として著作権侵害の有無を論じることはできない。」と述べて,著作権侵害を否定し,原告の請求をいずれも棄却いたしました。 |
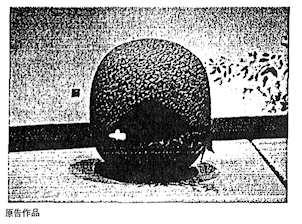
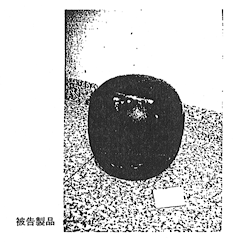
| 4.検討 |
|
著作権侵害の有無を判断する際には,その前提として,著作権が保護する対象は著作物の表現部分であり,表現の背後にあるアイディア部分は保護の対象とならないということが,しばしば強調されております。
本事件においても,この点が問題となり,被告製品は,原告作品の表現部分を複製しているのか,あるいは単にアイディア部分が共通しているにすぎないのかが争われています。 この点を明らかにするためには,まず,作品中のどの部分が保護すべき表現部分であり,どの部分が保護の及ばないアイディア部分であるのかを,明らかにすることが必要です。 作風やイメージが共通していても,著作権侵害は成立しないとよく言われますが,これは,アイディア部分のみが共通していることによるものと考えられております。 本事件は,このような争点に対して一定の判断を示した事例といえますが,表現とアイディアの分離の基準について具体的な判断を下した事例の一つとして重要であると考えられます。 |