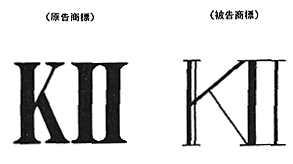
| 知的所有権判例ニュース |
| 商標権侵害差止請求事件において,当該商標 の登録手続き中に原告が行った主張と矛盾す る主張をすることが,信義則に反し許されない とした東京地裁判決 |
|---|
| 名越秀夫/生田哲郎 |
| (事件の内容) |
原告は,指定商品を第13類(手動利器,手動工具,金具,ただし平成3年改正前)とする後記1記載の登録商標(登録番号2521750号)(以下「原告商標」という)を有していました。被告は,平成元年ごろからカミソリ刃およびその包装に後記2記載の商標(以下「被告商標」という)を付し,また,これを付したカミソリ刃を製造していました。そこで原告が,被告に対し,原告商標権に基づき,被告商標を使用することの差止めを求めたのが本訴です。
|
| (争点) |
本件の争点は,第一に原告商標と被告商標が外観上類似するか否か,第二に原告商標の登録手続き中に,原告が,原告商標は文字商標ではなくモノグラムであり一種の図形商標であると主張し,かつそれが認められて登録された場合において,差止訴訟に至って,原告が,原告商標は,外観上,文字と認識されるというような従来の主張と矛盾した主張をすることが許されるか否かという点にありました。なお,原告は称呼,観念の類似性については主張しませんでした。
|
| (裁判所の判断) |
|
1.原告商標と被告商標の類否について
原告商標は,あらかじめそのようなものとして説明を受けていれば,ローマ数字の「II」の左側にアルファベットの文字「K」が接合したものと判別できないわけではないものの,細かく見ると様々な違和感があり,予断なく虚心に見れば一個の特殊な図形と認識されること,これに対して被告商標はアルファベットの「K」とローマ数字の「II」を普通の活字体で,近接並立させたものであり,両者の外観は類似しないと判断しました。 2.原告の主張が信義則に違反するかどうかについて (1)判断の前提 前記のように裁判所は,原告商標と被告商標とは外観上非類似であるとしつつも,仮に,あらかじめ説明を受ければ,原告商標は「K」と「II」の結合と判別できないわけではないという点につき,以下のような事実認定および法律判断をしました。 (2)原告商標の登録の経過 原告商標は,その登録手続きの過程で異議申立てがありました(なおこの異議申立人は本件の被告と同一人です。)。その中で異議申立人は,原告商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた商標であるので,商標法3条1項5号に該当し,また,片仮名で「ケイツウ」と横書きしてなる構成の異議申立人の登録商標(登録番号1863235号)と類似し,かつ指定商品も抵触するので,同法4条1項11号の規定に該当し,原告商標登録出願は拒絶されるべきである旨主張しました。 これに対し被申立人(原告)は,原告商標はモノグラム化して表したものであり,これを一見して,直ちに構成文字を明確に判断することはできないもので,全体として一種の図形よりなる商標と認識されるものとみるのが自然である。従って,本願商標を,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標とは判断できない。また本願商標からは特定の称呼,観念は生じない。従って原告商標と前記申立人の登録商標とは,称呼,外観,観念のいずれにおいても類似しない旨答弁しました。 審査官は,原告商標は,アルファベットの一文字「K」とローマ数字の「II」とを普通の態様で表したものとは認識しえない程度に特異に構成されているから,原告の創作に係る特殊な図形と判断し,異議申立ては理由がなく,原告商標を登録する旨の査定をしました。 (3)信義則違反の判断 以上の事実認定のもとに,裁判所は,原告が差止訴訟の裁判において「原告商標は『K』と『II』をくっつけた構成である」と主張したことに対し,出願登録の過程においては,原告商標はモノグラムであって一種の図形よりなる商標であるとして,それを構成する「K」,「II」の文字をくっつけたものであることを実質上否定する主張をして,それが認められて商標権を取得した原告が,本件訴訟において,掌を返すように原告商標は外観上「K」と「II」の接合体と看取できると主張して,被告商標がこれに類似する旨主張することは信義誠実の原則に反し許されないものであることは明らかであると判示しました。 |
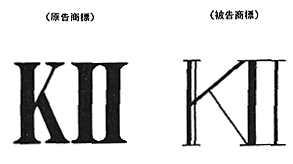
| (解説) |
|
File Wrapper Estoppel,いわゆる出願書類(包袋)禁反言の原則は,英米法での確立した原則であり,Fair Playの精神に根拠を有します。これと同様の考え方は,わが国においても「出願の経過参酌の原則」の一適用として特許法上確立したものと考えられています。わが国ではこの法理の根拠は,民法第1条第2項の「権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に之を為すことを要す」という規定に求められます。そしてこの「出願の経過参酌の原則」は,過去,特許法のみならず,実用新案法や意匠法においても認められてきたものですが,本判例は商標法においてもこれが妥当する旨を明示した点において大変興味深く,かつ影響が大きいものと思われます。
|